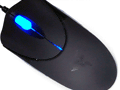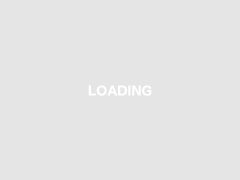�ƥ��ȥ�ݡ���
��ǯ��̾���ܺǿ���������Diamondback 3G�ץե������ȥ���ץ�å����
 |
������4Gamer�Ǥϡ�Diamondback 3G�μµ���Razer�������ꤷ��Ʊ�Ҥˤ����Ĥ����´ط����ǧ���ʤ��餷�Ф餯���äƤߤ��Τǡ��ޤ��ϥե������ȥ���ץ�å������Ϥ��������Ȼפ���
�������ʤ�Ʊ�����ǡ��ǽ��������ۤʤ볰��
������DeathAdder�Ȥޤä���Ʊ�����������
 |
 |
�����ʤߤˡ��ޥ��������֥��ޤ���ν��̤�4Gamer�ˤ���¬�ͤ�Diamondback 3G��122g����Diamondback��126g��������ޤ�������¤���Ѳ��ϡ���̯�˽��̤رƶ���Ϳ���Ƥ���褦������äȤ�ɮ�Ԥˤϡ�4g���٤ΰ㤤���δ��Ǥ��ʤ��ä�����
 |
 |
����Diamondback�Ǥϡ�����2�Ĥ����Ѱդ���륵���ɥܥ����¼�Ū�ˡ֤��줾��1�Ĥ��礭�ʥܥ����äơ�����ξü�˥����å�������פȤ����ü���߷פȤʤäƤ��ꡤ���줬ʪ�Ĥ�����������������ҤΤȤ��ꡤƱ���������Ƥ��뤳�Ȥ⤢�äơ��������˿����ʤ��ѹ��Ϥʤ����Ĥޤꡤ��¦��ü�ˤ���ܥ�������Ȥ��ơ����ξ���Ȥ�ȿ�����Ƥ��ޤ��Ȥ������ä���ߥ��ϡ���ǰ�ʤ��鿷��ǥ�Ǥ⽽ʬȯ��������Ȥ������Ȥ������Τ�����ϡ��Ť��߷פθ³��Ȥ��������Ǥ��롣
 |
����3�����ֳ���������ʹ���ơ���Razer DeathAdder���ʰʲ���DeathAdder�ˤǺ��Ѥ�������Ȥʤä��Τ��Ƥ���ͤ�¿�������������Υ����˴ؤ���Razer����Diamondback 3G��DeathAdder�ǤϤޤä���Ʊ����������Ѥ�������������롣Razer DeathAdder���ȡ�1800/900/450dpi��3�ʳ��եȥ�����Ū���䴰�ʤ��˼¸�����Τ����������Diamondback 3G��800dpi��Ʊ���ǡ������ޤǥϡ��ɥ�����Ū�˼¸�����Ƥ���ȤΤ��Ȥ���
�����ΤȤ��ƥϡ��ɥ������ϡ������ͽ�۰ʾ�˵�Diamondback����ħ���Ĥ��Ƥ��롣24��ߤΥ���Ȥʤ�����������ۥ�����Ϥޤä���Ʊ����ΤǤϤʤ����Ȼפ��ۤɤǡ���Diamondback�Υ桼�����ʤ顤���������˰��´���Ф��뤳�ȤϤޤ��ʤ��ΤǤϤʤ������������ʤ�ȯǮ�ǡ�Ĺ���ֻȤäƤ���Ȥۤ�Τ겹�����ʤäƤ������Ͼ������ˤʤä��������Τ�����ϴ�������꤫�⤷��ʤ���
���ʤ�������Diamondback�μ�ʥ��ڥå��ϰʲ��ΤȤ��ꡣ
 |
����Ū�ˤϡ֤��Ĥ��������ܡפ���
�����Ĥ���ħŪ����ʬ��
 |
������������äƤϡ����־�ˤ����SENSITIVITY�ס�SCROLL WHEEL�ס�BUTTONS�פΥ��֤��ڤ��ؤ���ȡ����ƥ��ӥƥ������֥륯��å�������������ۥ����롤�ܥ��������Ƥ���������äƤ����롣�ޤ������������꤬���ƥ��ӥƥ��Ρ�Advanced�ץ�˥塼�˰ܤ�ʤɡ��鸫�Ǥ�ʬ����ˤ����Ϥ����֤��ä��Ƥ���褦�������⤽��ݡ���졼�Ȥ�������ܤ��ʤ��ä��ꡤ�ץ��ե�����γ�ǰ��ʤ��ä���ȡ��ɤ��餫�Ȥ����Х���ȥ�桼����������ʷ�ϵ�����ĥ���ȥ�����ѥͥ�������դˤ��줬����äĤ��䤹���ˤĤʤ��äƤ��롣
���ޤ����ܤ������Τϡ���DiamondbackƱ�͡����åץǡ����оݤ��ɥ饤�Х��եȥ����������ˤʤäƤ��ꡤ�ե����०�����åץǡ��Ȥ���褦�ʻ��ͤˤϤʤäƤ��ʤ����������˽������ʤȹ�碌���Τ�������ȥ�桼���������ꤷ����̤ʤΤ���ʬ����ʤ���������Razer���ޥ����˿����褦�ʿͤˤȤäƥϡ��ɥ�ι⤤�ե����०�������åץǡ��Ȥ���ά����Ƥ���Τϡ�����˰յ������롣
 |
 |
 |
 |
��ɸ�������ԤäƤ��뤦��������ʤ������ǡ�����Ƨ�߽Ф����Ȥ������ü�����٤ι⤯�ʤ�SENSITIVITY�Ρ�Advanced Sensitivity Settings�ץ�˥塼�����ġ����Ƥ����Τ�ʬ����ʤ����������Ѥ�餺�Ǥ��롣�����ʤ��Master Sensitivity Control�ס�Master Accel Control�ס�Master Windows Control�פȸ����Ƥ⡤���̤Ϥޤ�ʬ����ʤ���
��Diamondback 3G�ǽ��ƥ����ޡ������ޥ����˿����ʤ顤�ޤ���ɸ������ΤޤȤäƤߤ뤳�Ȥ�뤬���⤷�����������ꤷ�Ƥߤ����ʤä��顤�ʲ��ν�����ꤷ�Ƥߤ�Ȥ������������ѹ��������Apply�פΥ���å���˺��ʤ���
- ��˥塼�����ˤ�����������꤫��800/1800dpi�Τ����줫������
- Master Windows Control�ʢ������Windows�Υ���ȥ�����ѥͥ�ˤ���֥ޥ����פ�������Ǥ���ݥ���®�٤�100��Ϣư����ˤǡ��١����Ȥʤ봶�٤����ꤹ�롣�¤ä����������������
- �ޥ����ݥ��β�®�����ˤʤ�ʤ顤Master Accel Control�Ρ�on�פˤ�������å����ʤ���Dz�®�����դˤʤ롣��Υ������åȤǤϥ����å������äƤ���Τ������ա�
- �ޥ����ѥåɤη�������ͳ�ʤɤǡ��IJ��δ��٤���̤����ꤷ�������ϡ�Master Sensitivity Control�Ρ�on�פ�����å����ơ���X-AXIS�ס�X�Უ���ˡ�Y-AXIS�ס�Y��ļ��ˤ��ѹ�
���ޤ������˻�ǰ�ʤΤϡ�����ΰ�ĤǤ���Ϥ��Υץ�����ޥ֥�ޥ�����ǽ�������켫�ΤλȤ�����ΰ����ȡ������ऴ�Ȥ����꤬�Ԥ��ʤ��Ȥ�����Ĥ�����ˤ�ꡤ�����餯�ۤȤ�ɻȤ�ʪ�ˤʤ�ʤ����ȡ��ޤ����������ι⤤����������ࡤ���뤤�ϥ���饤����Ǥϥޥ����϶ػߤ���뤳�Ȥ�¿���Τǡ����¤Υ�����ץ쥤�ˤ����ƤϤ���ۤ�����ˤʤ�ʤ��褦�ʵ��⤹�뤬��
 |
 |
 |
�����Ȥ���ϥɥ饤�ФΥ��åץǡ����Ԥ�������Version 1.00�ɥ饤�Ф��ȡ�On-the-Fly Sensitivity�˴ؤ���ܥ���γ�����Ƥ������Ƥ�ͭ���ΤޤޤˤʤäƤ��ޤ��ʤɡ������Ĥ�����������������줿���ϡ��յ����Ƥ���������
����������Фʤ��Υ����ޡ������ޥ����Ȥ���
�ְ㤤�ʤ����Ťʡ�����������
���Ȥ����櫓�ǡ����ڥå��䥽�եȥ�����Ū�ʼ����ϡ���Ǥⲿ�٤���Ŧ�����褦�ˡ��㴳����ȥ�桼����������������Ƥ���Ȥ��äƤ褵��������������͵����ʤ������ǤǤ⡤Ʊ�Ҥκǿ��������ʤǤ���DeathAdder��Lachesis�Ȥ��ä�������ˡ��������̤���֤Ĥ���櫓�ˤϤ����ʤ��ä��Τ��⤷��ʤ���DeathAdder���о줷���Ȥ���������ΡȺ���Ȥ������ޡ��ɤ����줿�Ȥ�����ξ���б��ޥ����ο����Ȥ�����˾�ˡ�Razer�ʤ�ˤǤ����ϰϤDZ�������̤Ȥ⤤�������Ǥ��롣
���ܹƤ�Ω������Ū�ˡ��Ȥ�����ο�����ʬ�ޤǤ�Ƨ�߹��ޤʤ�������Diamondback�ΡȤĤޤ����ɤ˴���Ƥ���ͤʤ顤�ܹԤ˸��Ǥ����ȤϤʤ������������Τ�����ϡ�Ʊ�������鵯�����Ƥ�������Τ��ȤϤ���ȴ�������
��2007ǯ10��17�������μ������ʤ�7000��8000�����١������ޤǵ�ǽ�̤�ʤä��Τʤ顤�⤦�����²��Ǥ�褫�ä��Ȼפ�졤��������������ǰ���������Ĥ�Diamondback�˼椫�줿�����뤤�ϰ��Ѥ��Ƥ����ͤˤȤäƤϡ��ְ㤤�ʤ���̣�Τ��������Ǥ���
���Ǥϡ��ǿ�����Υޥ����Ȥ��ƤϤɤ����ä����ͤ�����Τ���Ƨ�߹�����Ȥ�����ˤĤ��Ƥϡ��⤦�����ƥ��ȴ��֤���äƤ��顤���餿��Ƥ������������Ȼפ���
- ��Ϣ�����ȥ롧
 Razer
Razer
- �������URL��
Copyright (C) 2023 Razer Inc. All rights reserved
- Razer DeathAdder Elite ���르�Υߥå� �����ߥޥ����������ݾ��ʡ�RZ01-02010100-R3A1

- ���쥯�ȥ��˥���
- ȯ������2016/12/23
- ���ʡ�