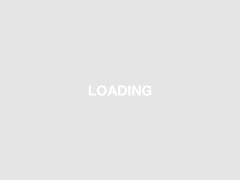業界動向
Access Accepted第482回:2015年の欧米ゲーム業界を振り返る
 |
2015年も残すところ10日ほど。年内の本連載も,今週を含めて2回を残すのみとなった。というわけで,今週は今年起きた出来事やニュース,トピックなどを海外在住者からの視点でまとめてみたい。ファンやゲーマーから愛された経営者が舞台を去ったり,北米で熾烈な戦いを繰り広げる据え置き型のコンシューマ機に大きなな動きがあったりなど,振り返ってみれば,2015年もいろいろなことが起きた。筆者のようなPCゲーマーにとって嬉しい話も,いくつか聞かれたようだ。
健闘中の据え置き型コンシューマ機
この記事の掲載と前後して,「Steam」を始めとするゲーム配信サイトでは,翌年まで続くウィンターセールが始まる。ゲーマーにとって気の抜けないショッピングシーズンはまだ続くわけで,セールをやっているサイトをチェックしたり,ゲームを買ったりするのに忙しく,肝心のプレイ時間が取れない,という読者も少なくないかもしれない。だが,たっぷり遊べる年末年始のお休みまではあと少しだ。
2015年の北米ショッピングシーズンの販売結果などはまだ出ていないものの,流れてくる情報を見る限り,PlayStation 4とXbox Oneは好調のようであり,発売から2年を経て,北米ゲーム市場を牽引するメインプラットフォームがしっかりと切り換わったことは間違いなさそうだ。
ソニー・コンピュータエンタテインメントの発表によれば,11月24日の時点でPlayStation 4の販売台数が世界累計で3020万台に達したとのこと(関連記事)。これは,各店舗が大きな売り上げを記録す「ブラックフライデー」の直前の数字にあたり,この後,約1か月にわたって続くセール期間を加えると,販売台数はさらに増えるはずだ。おそらく,数百万台の上乗せになるだろう。
 |
2013年の発売開始から6週間で,PlayStation 4の販売台数は420万台だった。ユーザーのうち,例えば10%が同じゲームを購入すれば,販売本数は46万本になり,セールス的には「まあ,そこそこ売れた」というレベルだ。しかし,現時点でユーザーの10%が同じゲームを買えば販売本数は300万本を超え,いわゆる「AAAタイトル」と呼ばれる,大きな予算を投入したゲームでも十分にペイできる数字になる。わずか2年で,そこまで成長したわけだ。
販売台数がアクティブプレイヤーの数をそのまま反映しているわけではないし,時間の経過でゲームライブラリが充実すれば,10%は,8%,5%と減っていくだろう。しかし,それを考えても3000万台という大台の数字は,欧米のパブリッシャやデベロッパにとって十分魅力的で,PlayStation 4向けタイトルだけでも回収が見込める,大きな市場が確保されたことになる。
 |
一方のMicrosoftは,「意味のない比較である」という判断から,2015年7月に「世界で1400万台が流通している」とアナウンスして以来,Xbox Oneのセールスについて具体的な数字を挙げることがなくなった。日本やヨーロッパ市場では苦戦しているようだが,2016年までに世界累計の販売実績が,2000万台近くに達すると見るメディアは多い。これは,現状のPlayStation 4と比較しなければ十分な成績であり,過小評価すべきではない。
実際,北米では2015年の中頃まで,月々のXbox Oneの販売台数はPlayStation 4のそれを超えていたし,12月に入ってからは299ドルのショッピングシーズン割引きが始まり,そちらも好評の様子だ。2016年にリリースされるファーストパーティタイトルやエクスクルーシブタイトルを中心に,来年は本格的な巻き返しを図ると思われている。
筆者的な2015年のビッグニュース
さてここで,筆者が個人的に2015年のゲーム市場におけるビッグニュースだと感じる事柄を5つ,簡単に紹介してみよう。
(1)岩田 聡氏逝く
任天堂の岩田 聡代表取締役社長の逝去については,北米でも大きく報道された。筆者は,2005年のGame Developers Conferenceの基調講演で岩田氏が述べた「名刺の上では,私はゲーム企業の社長です。頭の中では,私はゲーム開発者であると思っています。しかし,私の心はゲーマーなのです」という言葉に,詰めかけた数千人のゲーム開発者達が地響きのような歓声をあげたことを,今でも忘れない。
ゲーム業界において,彼ほど個人として愛された経営者はそういないだろう。この大きな穴を,任天堂が今後どのように埋めていくかにも注目が集まっている。
関連記事:任天堂の岩田 聡代表取締役社長が逝去
(2)Xbox OneがXbox 360作品との互換性を実現
Xbox 360向けにリリースされたタイトルとのバックワードコンパティビリティ(後方互換性)を,Xbox Oneが実現させた。「リマスター版」というビジネスが使えなくなるパブリッシャにとっては微妙かもしれないが,「Halo」や「Gears of War」シリーズはもちろん,「Fallout 3」や「BioShock Infinite」など,100作以上がプレイ可能になるのは,ゲーマーにとって嬉しい話だ。Xbox Oneの今後のセールスにとっても,これは強い追い風になるだろう。
関連記事:Xbox Oneが後方互換性を獲得。Xbox 360のタイトルがそのまま遊べるように
(3)FFVIIのリメイク版,さらにシェンムーの最新作が発表
発表と同時に北米のゲーマーを熱狂させたのが,スクウェア・エニックスがアナウンスした「FINAL FANTASY VII REMAKE」と,鈴木裕氏の「シェンムー III」だ。「シェンムー III」は,クラウドファンディングで,実に630万ドルという記録的な開発資金の調達に成功している。どちらも,日本のゲームが最も元気だった頃に生まれた作品のリマスターおよび続編で,最近あまり存在感を発揮できていない日本産タイトル復活のきっかけにもなるかもしれない。
関連記事: 完全リメイク版「FINAL FANTASY VII」がいよいよ登場。PS4にて先行リリース
関連記事:鈴木 裕氏の新作「シェンムー III」が発表。アナウンスと同時にKickstarterでの資金募集がスタート
(4)PlayStation 4が「Call of Duty:Black Ops III」の時限独占を獲得
本連載第435回「Xboxと香水。独占的マーケティングについて考える」で紹介したとおり,2009年の「Call of Duty Modern Warfare 2」で,時限独占という新たなマーケティング手法を開発したMicrosoftだったが,その6年後,同じ「Call of Duyt」シリーズの最新作で,ライバルのソニー・コンピュータエンタテインメントに同じことをやられてしまった。
今後,ビッグタイトルをめぐるプラットフォームホルダーの駆け引きはさらに熾烈になりそうで,その嚆矢ともいえる出来事だろう。
関連記事:Xboxの牙城崩れる? 「Call of Duty:Black Ops III」の時限独占権をSony Computer Entertainmentが獲得
(5)小島秀夫氏がコナミデジタルエンタテインメントを退社
小島秀夫氏とコナミデジタルエンタテインメントの関係は,以前から海外メディアで頻繁に取りあげられており,同氏の退社を伝えるニュースに驚きはなかったものの,直後の「コジマプロダクション」設立とソニー・コンピュータエンタテインメントのバックアップによる新作の開発は,北米でも大きな話題になった。
日本におけるゲームメーカーとクリエイターの関係に一石を投じる,重要な出来事だ。
関連記事:小島秀夫氏が新スタジオ「コジマプロダクション」を設立。SCEと契約を締結し,第1作はPlayStation 4独占タイトルとしてリリースへ
PCゲームがまた楽しくなった
さて,そんな2015年を振り返って,筆者を最もウキウキさせているのは,PCゲーム市場が目に見えて活気を帯び始めたことだ。満を持して(?)リリースされた「Windows 10」は,思ったほど安定性に優れているわけではなかったが,インタフェース回りの使いやすさや,統合されたXbox Liveアカウント,そして,SteamやGoG.comなどとの相性の良さが光っている。
PCゲーマーの強い味方である「Steam」の利用率も向上しており,Valveが公開しているユーザー統計によれば,10月31日には1348万の同時アクセス数を記録したという。「Dota 2」「Counter-Strike: Global Offensive」,そして「Team Fortress 2」など,Valve作品に人気が集まっている感じはあるが,11月11日に欧米で発売された「Fallout 4」の同時プレイ数が44万6000人に達し,PC向けにリリースされた「Grand Theft Auto V」の約36万を軽く塗り替えてしまうなど,PCゲームの人気は右肩上りだ。
そのValveは今年,ついに「Steam Machine」を発売した。上記の統計によれば,Steam Machineを購入した人に,Linuxマシンを自作してゲームを楽しんでいる人を加えても,全体の1%未満で,相当なマニアでもない限り,WindowsからSteam Machineに乗り換えたというゲーマーは少ないようだ。日本での展開は現在のところ発表されていないが,これに対してValveが次の手をどう打ってくるのか,しっかりと追っていきたい。
「Steam Machine」以上に筆者にとって印象深いのが「Steam Link」の発売だ。「Steam Link」とは,Windows 10を搭載したPCで動いているゲームの映像を,リビングルームのテレビにストリーミングできるデバイスで,コントローラを接続して使う。筆者の場合,少しでも安定したプレイを楽しもうと,ワイヤレスではなくPLCアダプタ(コンセントLAN)を使っているが,「Fallout 4」や「ARK:Survival Evolved」など,最近の人気作に加えて,「Darkwood」や「Kingdom」などのインディーズタイトルが,大画面でソファに座りながらプレイできることに軽い感動を覚えている。
「もう,欲しいゲームはたいてい買いつくしたよなあ」と思いつつも,オンライン配信サイトのウィンターセールをチェックしてしまうのは,そんな「Steam Link」がもたらしたゲーム環境の変化に関係しているのかも知れない。いずれにしろ,PCゲーマーにとって2015年は転機の年として記憶されるだろう。
著者紹介:奥谷海人
4Gamer海外特派員。サンフランシスコ在住のゲームジャーナリストで,本連載「奥谷海人のAccess Accepted」は,2004年の開始以来,4Gamerで最も長く続く連載記事。欧米ゲーム業界に知り合いも多く,またゲームイベントの取材などを通じて,欧米ゲーム業界の“今”をウォッチし続けている。
- この記事のURL: