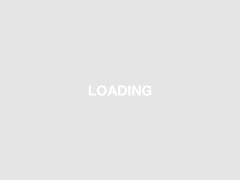イベント
手のひらの水に“推し”が出現する技術に驚く。Inter BEE 2018&デシタルコンテンツEXPO 2018レポート
Inter BEEは,正式名称が「国際放送機器展」であることからも分かるとおり,元々は放送や映像に関する技術や機器の展示会である。そこに,従来は単独で行われていたイベントのデジタルコンテンツEXPOが合流したわけだ。展示会場には区切りがなく,来場者は自由に行き来できることもあって,映像とデジタルコンテンツの関係をよく表しいるように思えた。
 |
 |
一方,デジタルコンテンツEXPOは文字通り,先進的なデジタルコンテンツの展示会であり,雰囲気は東京ゲームショウ2018にあったインディーゲームコーナーをより尖らせたようなものだ。
本稿では,こうした両イベントから,ゲーマーに関係ありそうなものを中心にレポートしよう。
 |
 |
水面上に浮かぶ映像を,水ごと手ですくい上げられる「FairLift」
 |
電気通信大学の情報学専攻小泉研究室のブースでは,「水面反射を用いた空中像とのインタラクション」という展示があった。水上に映像が浮かんでいるように見えるという映像投影システムで,体験者が特別なデバイスを持つ必要はなく,水に何かを混ぜたり,水中に特別な機器を設置する必要もないそうだ。
「FairLift」と呼ばれるこのシステムは,「再帰透過性光学素子」で空中に映像(空中像)を結像させて,その像を水面に反射させて表示するという仕組みとなっている。
再帰透過性光学素子と言われても,なんのことやらという人も多いと思うので,ごく簡単に説明しよう。交通標識や自転車の後部にある反射板は,浴びせられた光を反射して光るように見える。これは,光源からの入射光を光源のほうに戻す性質を持つ「再帰性反射材」というものを使っているためだ。鏡に対して斜めから光を当てても光源には戻らないが,再帰性反射材は,斜めからの入射光でも光源に戻せるというのが重要な違いである。
再帰透過性光学素子は,光を反射させるのではなく,透過させて特定の場所で結像させる用途に使える素子の一種だ。たとえば,小型プロジェクタの映像を再帰透過性光学素子経由で空中に結像させると,大きなサイズで投映するといったことが可能になるので,この仕組みを利用したサイネージなどが登場している。
FairLiftで面白いのは,空中像を水ごとすくい上げられるインタラクション要素があることだ。水面の映像を水ごとすくい上げると,空中像もその水に合わせて高さを変える。これは,水の真上に超音波センサーを設置して水の高さを認識し,それに合わせて光源の位置を自動調整することで実現しているという。体験として大変面白いものだった。
 |
 |
FairLiftでは,映像の投映元としてPC用ディスプレイを使用しており,カラー映像の投映も可能だ。表示装置の輝度が300nitあればいいそうなので,PC用ディスプレイはもとより,スマートフォンやテレビでも表示装置に使える。
と聞いて,「それならば,ゲームのキャラクターを水面に浮かばせることができるのではないか」と考えた人もいるだろう。答えはYesだ。
そこで,筆者がなかば信仰に近い形で敬愛するゲームキャラクターを表示させてみてもいいかと相談してみたところ,「そうしたくなりますよね!」と快諾を得た。大好き,電気通信大学。
 |
 |
 |
 |
また,インタラクション要素は,水面以外でも反射するもの,たとえばクリアファイルなどでも可能であるそうなので,ゲーム用途での展示やアトラクションに向いている。すくい上げたり持ち上げたり,あるいは少し移動させたときにキャラクターが反応するといった使い方も思い浮かぶ。ゲームイベントで空中像を出すというのは,東京ゲームショウや大規模なゲームイベントで使われる技術となるかもしれない。
食べられる素材でできた映像投映用デバイスはコラボカフェ向き?
 |
寒天や水,グラニュー糖といった食べられる素材で再帰性反射材を作り,それを使えば食べ物の上に映像を投映できるというもので,会場では,パンケーキの上にプロジェクションマッピングでキャラクターを表示する様子を披露していた。パンケーキを動かしても,映像がちゃんと追従していたのが見どころだ。
 |
 |
Hapbeatとは,音の振動を体に伝えることで,迫力や臨場感を感じさせるというデバイスだ。会場にあったデモ機は,ネックストラップの先端にHapbeatの特殊なバイブレータを取り付けてあった。このバイブレータは,既存の小型バイブレータよりも強力な振動を発生させることが可能であるという。
レースゲームを使ったデモでは,実際にエンジンの振動っぽい動きを体感できた。説明員によると,ゲーム用途においてはレースゲームやFPS向けを想定しているとのこと。
 |
なお,「Hapbeat(Necklace Ver.β)」が,Boothで販売中だ(※本稿掲載時点では品切れだったが)。こちらは製品版に近い形状となっており,気になる人はチェックしてみるといいだろう。
8K映像を扱うソリューションが増える
続いては,Inter BEE 2018の展示から,注目の製品や技術をピックアップしていこう。
2018のInter BEEでは,4K映像はもはや当たり前で,12月1日にスタートした新4K8K放送を背景に,8K対応をアピールする展示が目立った。8K放送が身近になるのは当分先の話だが,ゲームにおいて4K解像度が身近になるのは,そう遠い話ではない。
 |
 |
8K解像度で60pの映像となると,扱うには単純なCPUやGPUの性能だけでは済まない。CPUとメインメモリ,CPUと拡張機器,CPUとストレージなど,あらゆるデータ転送における帯域幅を確保することが重要な世界であるそうだ。デモ機の説明図を見ても,非圧縮の8K映像ソースを扱うには,今どきのハイエンドPCでもまったく足りないことが分かるだろう。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
メディアアート演出を手がけるアバクスは,研究開発部門である劇団エックス名義で,音に触れたり,動かしたりといった音を物体のように操作可能にした技術「Sonic User Interface」を出展していた。
展示ブースには,横に長く連結されたスピーカーが用意されており,その前で体験者は,VR HMD「Vive」のワンド型コントローラを手に持って立つ。
 |
そして体験者がコントローラを動かすと,コントローラの位置から音が聞こえてくるのだ。左右だけでなく,前後や上下の動きにも対応しており,ボールを上下に動かすデモは,ちゃんとその位置から音が聞こえてきた。
デモの様子を撮影した動画を,ステレオスピーカーやヘッドフォンで音を聞きながら見てもらうと,雰囲気が伝わると思う。カメラの内蔵ステレオマイクで音の動きを忠実に録音するのは難しいのだが,とくに後半では音の動きが聞き取りやすいだろう。
 |
また,任意の範囲に狙った音声を再生することもできる。たとえば,スピーカー正面の左側に立つと日本語の,右側に立つと英語音声が聞こえるといったことも可能だ。左側にいるときは英語音声がまったく聞こえてこないので,実に不思議な感覚だった。
 |
たとえば,横長のサイネージに,横に並んだゲームキャラクターの映像を表示しておき,あるキャラクターの前に立つとその声だけが聞こえる(※それ以外のキャラクターの声は聞こえない)といったことができるわけだ。
相応に規模の大きなシステムなので,ゲーマーが自宅に導入する技術ではないが,イベント向けのシステムとしては面白い。キャラクターの多いゲームのイベントやライブ向けに使えそうで,将来にはイベントの場で目にする機会があるかもしれない。
映像機器メーカーとして,その名を覚えている人もいそうなYUAN High-Tech Development(以下,YUAN)のブースでは,4K60p対応のキャプチャデバイスが展示されていた。中でも,USB Type-C接続タイプの「PD570 PRO HDMI2.0」がちょっと便利そうだ。
PD570 PRO HDMI2.0は,PCとの接続にUSB 3.0を用いるキャプチャデバイスで,映像入力は4K60pまで対応。録画はソフトウェア次第とのことだった。
 |
 |
そのほかに,M.2接続型のビデオキャプチャカードという珍しいものもあった。発想がどこか変態的だと思ったのだが,PCI Express対応のM.2スロットであれば仕様的には可能なので,コンパクトな筐体とマザーボードを使ったVol.デオキャプチャ専用PCというのはありかもしれない。
 |
 |
以下では,写真中心に,Inter BEE 2018会場で見かけたちょっと便利そうなPC用周辺機器や映像関連ソリューションをまとめて紹介しよう。
 |
 |
 |
 |
Inter BEE公式Webサイト
デジタルコンテンツEXPO公式Webサイト
- この記事のURL: