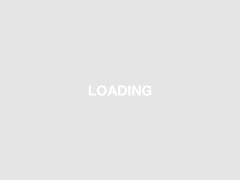イベント
「Flyers' Lab #1」聴講レポート。スマホ向けのヒットタイトルを手がけた開発者達が明かすシナリオ制作のポイントとは
 |
このイベントの前半では「シナリオをつくる上で大切にしていること,その事例」をテーマとして,f4samuraiの田口堅士氏,gumiの今泉 潤氏,Wright Flyer Studiosの古屋海斗氏が各社のゲームづくりにおける工夫や取り組みを紹介し,後半ではその3名が意見を交わす座談会が行われた。本稿でその模様をレポートしよう。
 |
gumi 今泉 潤氏によるプレゼン「冷静と情熱のあいだのゲーム作り」
gumiの今泉氏は,「冷静と情熱のあいだのゲーム作り」と題し,ビジネス(冷静)と自分のやりたいこと(情熱)の二つの観点から,シナリオ制作を含めたゲーム作りについての持論を披露した。
 |
今泉氏は,「ゲームとは,ゲームモデルと世界観の組み合わせ」と定義したうえで,「主流のスマホゲームのゲームモデルは,クエストとガチャシステムのループ」と説明。そのため世界観で差別化を図る必要が出てくるのだが,莫大な数のスマホゲームが溢れている昨今で,目立つものを作るのはそう簡単ではない。
ブラウザ型のスマホゲームが主流だった時代は,カードゲームが中心で,クエストとガチャのループというゲームモデルがそのままビジネスモデルとなっていた。もともとドラマの制作を手がけていた今泉氏は,そこに世界観と,それに沿った演出を加えることで差別化を図っていたという。
 |
例えば今泉氏の手がけた「任侠道」は,当時主流のオーソドックスなカードゲームの一つだが,ヤクザの世界を舞台としており,その世界観に沿って奪い合うアイテムを全国各地の女性という設定にしている。
しかし時代が進んでネイティブタイプのスマホゲームが主流になると,カードゲーム以外にもさまざまなゲームシステムが登場する。今泉氏は,「ゲームシステムにストーリーが絡まなければ,感動は生まれない」とし,まずシステムを考え,そこにどんな言葉を載せるのかを考えなければならないと説明した。
 |
今泉氏は,自分が使っているキャラクターとフレンドの助っ人キャラクターが被ると醒めてしまうそうなのだが,そのため自身の手がける「ファントム オブ キル」(PC / iOS / Android)では,「イミテーション」という概念を作り,自分と同じ顔のキャラクターに出会ったら殺し合うという設定を作ったとのこと。
ほかにも,「ゲームとしてはよくあるシステムでも,現実と照らし合わせると不自然な点」は可能なかぎり説明できるような設定を加えているという。
さらに最近のスマホゲームは音楽や動画,ボイスを使うことが当り前となっており,そのうえIPタイトルとも競わなければならない。その中でオリジナルタイトルを展開するためには,ただ有名なクリエイターや声優を起用するだけではなく,「なぜこの人が音楽を手がけているのか,なぜこの人が映像を手がけているのかといったパッケージ感を出す必要がある」と今泉氏。それこそが,プロデューサーとしての手腕を問われるポイントというわけだ。
また今泉氏は,オリジナルタイトルにこだわる理由として「コンテンツとしての接触時間の長さ」を挙げた。すなわち,スマホは基本的に常に身に付けているデバイスであるため,必然的にスマホゲームの接触時間も長くなるというわけである。
今泉氏は「映画は,いかに莫大な予算を投じようとも数時間で消費されてしまう。その一方で,スマホゲームは誰かの人生のうち2〜3年,ひょっとしたらそれ以上接触してもらえる可能性がある」と説明し,「スマホゲームを基軸に,ほかのプラットフォームでも展開できる自社オリジナルIPを確立できれば」と意気込みを語っていた。
それでは,どのようにオリジナルタイトルを作るのか。今泉氏のイメージは,「50%は置きに行く,50%は自分が面白いと思うこと」だという。
すなわち半分は「今なら,これが受けそう」「今,これが流行っている」といったビジネス視点で,残りは自分のエゴをむき出しにして考えるわけだ。このバランスを崩して,たとえばビジネス視点を強めると,商売っ気が何となくプレイヤーに伝わってしまい,うまくいかないケースが多いとのことである。
今泉氏がオリジナルタイトルを企画するにあたって重視する4つのポイントも紹介された。
一つは,「ギャップを作る」ことで,組み合わせの妙こそが企画になるという。
また「イラストを作る」ことも重要で,例えばRPGであれば,多くの人が思い浮かべる大手コンシューマRPGメーカーのようなテイストは避けるとのこと。例えば「ファントム オブ キル」では,中世という王道の世界観の中に,敢えてジーンズの似合う女の子を組み合わせ,ほかに例のないテイストを生み出した。
さらに「映像を作る」こともポイントとなる。これは短時間で伝えられる情報量がもっとも多いからとのこと。
そして「キャッチコピーを作る」。これは物語の奥行きをイメージさせるもので,ゲームがほとんどできていない段階であっても,それっぽく作っているそうだ。
加えて,オフラインイベントの重要性についても言及があった。今泉氏は,「コンテンツを作っている人達は,人前に出るべき」とし,「そうしないとフィードバックも批判も得られず,成長できない」と語っていた。
 |
最後に今泉氏は,「ストーリーとは何か」を語った。「ゲームのストーリーやシナリオは,テキストだけで伝えるのは難しい」とし,「それらは,キャラクターを輝かせるためだけに存在すればいい」「キャラクターこそがIPの軸」との持論を披露して,プレゼンをまとめた。
古屋海斗氏によるプレゼン「プレイヤーが体験する物語」
Wright Flyer Studiosの古屋氏は,自身がディレクターを務めるスマホRPG「アナザーエデン 時空を超える猫」(iOS / Android)におけるシナリオ制作の事例を紹介した。
「アナザーエデン」は,基本無料のスマホRPGでありつつも,シングルプレイ専用の壮大なストーリーや,実際にプレイヤーが歩き回れるマップ,そして「クロノ・トリガー」などの名作RPGを手がけた加藤正人氏をシナリオに起用したことなどで話題を呼んだタイトルであり,300万ダウンロードを記録するほどの人気を誇っている。
 |
古屋氏によると,「アナザーエデン」におけるシナリオとは,単に「テキスト+演出」に留まるものではなく,そこに「ゲームプレイ」を加えたものであるとのこと。すなわちシナリオはゲームをプレイすることによって初めて完成するもので,古屋氏はどんな世界を冒険するのか,冒険の中で何を発見し,どんな体験をするのかを重視しているという。そしてそれこそが,プレゼンの掲題である「プレイヤーが体験する物語」というわけだ。
古屋氏は「プレイヤーが体験する物語」を実現するためのこだわりとして,「意表を突く」「想像力をフルに活用する」「システムを利用する」という3つの手法も披露した。
まず「意表を突く」は,プレイヤーに作業感を感じさせない構成を実現するための手法だという。古屋氏は,「指示されたとおりに動いて予想どおりの展開になったとき,作業感が生まれる」とし,「プレイヤーが予想していた以上の展開を用意するよう心がけている」と語った。
 |
 |
 |
 |
また古屋氏は,意表を突くためのポイントとして,「小さな予想外の展開をふんだんに入れるのではなく,大きなインパクトのあるネタを1つだけ入れる」「意表を突く瞬間はプレイアブルにして,プレイヤー自身に発見させる」ことを挙げていた。
次の「想像力をフルに活用する」は,濃厚なシナリオ体験のためにイベントを長くすると,ゲームではなく読み物になってしまい,プレイヤーに苦痛を与え,またインタラクティブ性も失われるジレンマを解消する手法である。なお,ここでいう想像力とは,作り手側のものだけでなく,プレイヤー側のそれも指している。
例えば,外伝「ふたりの騎士と祈りの魔剣」は,魔剣士ディアドラの人生を描くという内容だが,それを最初から最後までやってしまうと,上記のとおり冗長なものになりかねない。
そこで「アナザーエデン」チームは,ディアドラの人生のうち一部をブラックボックス化して描かないこととした。代わりにその前後をシナリオ化し,彼女や周囲の変化を描くことで,ブラックボックスとなっていた期間に何が起きたのかプレイヤーに想像させ,壮大な物語を読んだかのような印象を与えたのである。
 |
 |
古屋氏はこの手法のポイントとして,「想像するだけで感情を揺さぶるような部分を考え抜き,ブラックボックス化する」「ブラックボックス化する部分は可能なかぎり壮大に(どのみち描かないので工数の制限はない)」「説明不足になっては元も子もないので,想像させるための情報は十分かつ丁寧に配置する」の3つを挙げていた。
 |
最後の「システムを利用する」は,「システムの制約でシナリオに制限が生ずる」「システムのせいで世界観が崩れる」といった状況を逆手に取り,シナリオや世界観を強化する手法である。
例えば「アナザーエデン」の「アナザーダンジョン」は,キャラクターを育成するためのいわゆる周回コンテンツであり,一般的なスマホゲームであれば世界観やシナリオとはあまり絡まない存在になっている場合もある。
 |
しかし「アナザーエデン」では,「名無しの少女」という記憶をなくしたNPCを用意し,プレイヤーのアナザーダンジョンの周回数が増えると,彼女が次第に記憶を取り戻し,また彼女とアナザーダンジョンの関係が明らかになるという設定を作ったのである。
つまり,周回コンテンツをゲームの世界観に沿ったストーリー仕立てにし,周回プレイにキャラクター育成以外の意味を持たせたというわけだが,結果としてプレイヤーから大きな反響が寄せられたという。
 |
古屋氏は,システムを利用するポイントとして,「システムの制約をチャンスと捉える」「常識だと思われがちなシステムこそプレイヤーを驚かせるチャンス。積極的にシナリオガジェットとして利用する」「それにより,もっと世界観が深まる仕掛けを考える」の3つを挙げていた。
スマホゲームのシナリオについて意見が交わされた座談会
後半の座談会は,「消滅都市」(iOS / Android)シリーズのディレクターであるWright Flyer Studiosの下田翔大氏をモデレーターとしたパネルディスカッション形式で行われた。
 |
最初のテーマ「シナリオや演出を考える際,着想はどんなところから得ている?」では,まず今泉氏は映像を思い浮かべるとのことで,例えば「ファントム オブ キル」では,「同じ顔の女の子が殺し合っている図はドラマチックだな」と考えたという。
一方,田口氏は自身から発想することはあまりなく,誰かの「こんなシナリオにしたい」という意見に「こうしたらどうか」と提案していくケースが多いとのこと。
そして古屋氏は,過去にゲームで遊んだときに得られた体験を自身の中できちんと分析・解釈し,新しいゲームとして再現することに努めているそうだ。また,映画館でそれほど面白くない映画を観ているときに,全然関係ないアイデアが浮かんでくることがあるとも話していた。
 |
「何のために『物作り』をしているの?」というテーマでは,今泉氏が「僕が作ったゲームを1日7分遊んでいる人がいるとしたら,その人を7分間殺しているのと同じ」とし,「だからこそ魂を込めたものにしなければならない」と語った。また不特定多数のプレイヤーを感動させられることも,大きなモチベーションになっているという。
田口氏はf4samuraiの設立後3年間は非常に苦労したので,その生活から抜け出すためにゲームを作っていたと明かした。その後「f4samuraiのタイトルを遊んだおかげで,ニートから社会復帰した」という感想を寄せられたことをきっかけに,「人々を応援するようなゲーム作り」を心がけるようになったそうだ。
 |
古屋氏は,自身がこれまでゲームをプレイすることで得てきたものを,今度はほかの人に与えられるようなゲームを作りたいと話す。また「ゲーム業界に貢献したい。恩返しがしたい」とも語っていた。
最後のテーマは,「スマホゲームのシナリオは今後どうなっていくの?」というもの。ここでは,長年サービスが続くタイトルにおいて,3名の登壇者がどのようにシナリオを作っていくのかという考えが披露された。
田口氏は,「従来のような積み重ね型のシナリオではなく,ゲーム全体を舞台装置にするような大きな仕掛けを作りたい」とコメント。例えばドリフターズのコントのように,プレイヤーが階段だと思って登っていったら途中で滑り台になって落ちてしまう,といったシナリオもシステムも込みの仕掛けとのことで,さらにはそれをリアルイベントにつなげることも視野に入れているという。
今泉氏も田口氏に賛意を示し,「スマホゲームのシナリオは行くところまで行ってしまった。それこそ加藤正人さんや奈須きのこさんのようなレジェンドが入ってきて,僕達はどうすればいいんだという状態」「今やボイスや動画はあって当り前で,セールスポイントにならない」と,現状をあらためて説明。
その状況を打破するには,シナリオとシステムを連動させるなど仕掛けを作っていかなければならないとし,具体例として「ドラゴンクエストIV」の第3章におけるトルネコとその奥さん・ネネのやり取りを挙げた。今泉氏は「ネネは,トルネコのそのときどきの状況次第でセリフが変わり“いい嫁”感が伝わってくる」とし,「これがただのシナリオだったら全然面白くならない。古屋さんや田口さんのおっしゃるシナリオとシステムの連動があるからこそ,プレイヤーの心に残る体験になっていく」と語った。
 |
古屋氏は,スマホが生活に密着したものであることを利用した,リアルと連動するシナリオが登場するのではないかと予想した。例えば,最初は悪魔を召喚するだけのアプリなのだが,日々それを起動しているうちにプレイヤーが事件に巻き込まれるといった展開をシナリオとして落とし込んだものとのことで,古屋氏は「自分で作るのか,それとも誰かに先に作られて悔しい思いをするのか」と話していた。
会場では,聴講者が登壇者に質問するコーナーも設けられた。「長年サービスが続くタイトルで,シナリオを書き続けるのはしんどくないか」という質問には,登壇者全員が「最初から終わりを決めている」と回答。
今泉氏は「スマホゲームが忘れ去られるのは,物語を描ききらないから。描ききられなかった物語に,人は思い入れを抱かない」と持論を語った。
田口氏は「物語が終わってプレイヤーが離れていくのは,それで十分満足したから」とし,「そのあと続編なり外伝なりを作ればいい」と考えているという。
古屋氏は,アップデートやDLCなどで追加コンテンツが提供されなかった時代のコンシューマゲームを引き合いに出して,「当時のゲームは,その気になれば手に入れたその日にエンディングまで見ることもできるものもあった」とし,「『アナザーエデン』でも終わらせないようにするよりは,次を作ろうと考えた」と話していた。
そのほかこの座談会では,「大ヒットしたフィーチャーフォンのソーシャルゲームでも,人々が持つデバイスがスマホに変わったら忘れ去れてしまう。そうした世代交代の壁を越えられるのは世界観だけだと思うので,意識してしっかり作っている」(今泉氏),「古屋が『クロノ・トリガー』はいいといっていた翌日に加藤さんが来社した。これは運命だと感じた」(下田氏)という話も飛び出した。
 |
Flyers' Labは,今後も定期的に行われる予定で,11月13日にはヨコオタロウ氏と加藤正人氏をゲストに招き,Flyers' Lab #2 「世界観編」 ヨコオタロウ×加藤正人 『ゲームの世界観を語る!』を開催するとのことだ。
Flyers' Lab #2 「世界観編」
ヨコオタロウ×加藤正人『ゲームの世界観を語る!』
- この記事のURL: