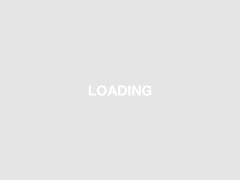すごろくやは,最新の日本語訳付き海外産ボードゲームを先行体験できるイベントを,2020年1月25日にイベントスペース
「す箱」で開催した。
今回のイベントは「じっくりゲーム『ストーンデイズ』を買ってすぐ遊ぶ会」と「じっくりゲーム『ファイナルアクト』を買ってすぐ遊ぶ会」の2部構成となっており,各部で表題の新作タイトルをプレイできるというもの。
表題の
「ストーンデイズ」「ファイナルアクト」はいずれもイスラエルのTyto Gamesが出版した作品だ。本稿においては,そんな両作品のゲーム内容を紹介していく。
同時に動くコマの移動先を読んで棍棒を叩き込む。特殊能力も豊富な協力&対戦ゲーム「ストーンデイズ」
ストーンデイズは新石器時代を舞台とする戦略シミュレーションで,プレイヤーは2つの部族のいずれかに所属(2人プレイの場合は1対1,3人以上の場合は1つの部族を2人で協力して操作する)し,土地の支配権を奪い合う。
チーム戦と1対1の形式を選べるということで,せっかくなので今回はチーム戦でプレイ。ちなみに筆者が所属したのは誇り高き“ブラックウォーター・クラン”で,相手方は“ゴールデンスピリッツ・クラン”だ
 |
| タイトル |
ストーンデイズ / Stone Daze |
| 価格 |
6380円(税込) |
| メーカー |
Tyto Games |
| デザイナー |
Sharon Katz & Lior Keinan |
| 対象年齢 |
10才~大人 |
| プレイ人数 |
2~4人用 |
| 所要時間 |
45~60分 |
戦いの舞台となるのは,横12マス,縦12マスで構成されるゲームボード。自分のクランに所属する
「原人コマ」を進軍させ,1人でも最奥の列(横列)に侵入させれば我々の勝利となる。逆に,相手クランの原人コマが一番手前の列に侵入すると敗北だ。
ゲームを開始する前に,マップに障害物となる
「岩山」や
「沼」のタイルを配置していくことになる。岩山は後述する攻撃の射程に影響を与えるうえ,沼は特殊な能力を使わない限り通行が完全に不可能だ。マップを決めた後に原人コマの初期配置を決める形になるので,この時点ですでに読み合いが始まっていると言えよう。
各チームが配置できるのは,1マスの小さな岩山タイルが3枚,2マスを占有する大きな岩山タイルが2枚,四角い4マスの範囲を通行不能にする沼タイルが1枚となる。岩山タイルは木製で,かなりの厚みがある
 |
 |
すべての配置が完了し,各陣営に7枚の
「操作パネル」が配られたらゲームスタート。今回のように2人チームで戦う場合は,1人が3枚,もう1人が4枚の操作パネルを分担する格好になる。
ではどうやって指示を出すのか。このパネルは磁石が張り付く仕組みになっており,アクションを示すアイコンにリング型の磁石を貼り付けることで秘密裏に行動を指定できる。7つの原人コマへの指示を出し終えたら「せーの!」でオープンすると,一斉に原人たちが動き出すわけだ。
操作パネルには自陣営に所属する原人の顔が描かれており,これが駒と連動している。それぞれの原人がなかなか個性的な顔立ちをしているので「ジイさん」「姉ちゃん」などと適当に呼び名を決めて動かすと,愛着が湧いて楽しいうえに場所を間違いにくいのでオススメ
 |
原人コマの移動先は「井」型の表にリング磁石を配置することで指定する。前進させるなら中心から見て上中央に置き,その場に留まりたければ中央に置く,といった具合だ。コマの方向を90度回転させたい場合は,顔の右下・左下にある矢印に磁石を置こう
 |
 |
 |
 |
ただし,操作パネルで指定できるのは移動先と特殊アクション(後述)だけで,各原人コマが“攻撃”を行う対象は操作パネルの各種指定が完了した後に改めて指定することになる。
ここで言う“攻撃”とは,原人コマが1ラウンドに1本だけ投げられる棍棒のことだ。投擲と侮るなかれ,彼らは自分から見て横3マス,前方6マスの広範囲にわたって,狙った位置へ正確に棍棒を落下させられる。なお,攻撃の処理は移動処理の後に行われるため,相手の移動先を読んで棍棒を投げなければならない。
各チームが持つ棍棒コマ。棍棒を投擲する位置を決めた後のゲームボードは危険地帯だらけの地獄絵図と化す
 |
 |
原人コマがダメージを受ける(棍棒がヒットする)と「たんこぶピン」が1本刺さり,たんこぶがついた状態でさらにダメージを受けるとゲームから除外される
 |
射程距離を目算で測るのはけっこう面倒だが,マップの隅には6マスごとに同じ色のアイコンがプリントされており,これが射程距離の目安となっている
 |
ここで重要になってくるのが,最初に配置した岩山タイルが持つ2つの特性だ。まず,岩山タイルは投擲の射線を遮る効果があり,攻撃側の原人から見て直線上に岩山タイルが置かれていた場合,その真後ろは攻撃できない仕組みになっている。要するに,岩山タイルの裏に隠れていれば安全というわけだ。
岩山タイルの裏に隠れている場合の攻撃範囲(直線1列のみ)。正面にいる相手からの攻撃に対しては安全になる
 |
ただし,岩山タイルの裏に隠れている原人は視線が遮られてしまうため,岩山タイルを含む前方3マスしか攻撃ができない。隠れてばかりいると,相手に進軍のチャンスを与えてしまう。
岩山タイルの真後ろに隠れている状態での攻撃範囲。安全ではあるものの,隠れてばかりいると戦線を押し上げられてしまう
 |
逆に攻撃的な運用方法も存在し,岩山タイルに乗っている原人は前方への投擲射程が+1される。たかが+1と感じるかもしれないが,ギリギリの距離で棍棒を投げ合っている状態では一方的な攻撃が可能になる。そのうえ,後退すれば安全な射程に逃げ込めるため,リスクを背負って岩に登る価値は十分にあるわけだ。
頭数の差で露骨に有利不利が傾くシステムなので,まずは弾幕を張って各個撃破を狙いたいところだが,射程距離の関係で攻撃を集中させるのは簡単ではない。原人の配置を集中させるのも不可能ではないが,無理をすれば手薄になった戦線を一気に突破されてしまう……。この厳しい読み合いとジレンマが本作のキモと言えるだろう。
相手が攻撃範囲に踏み入ろうとする前に岩山タイルに登れば,かなりのプレッシャーを与えられる
 |
そんな読み合いをさらに熱くするのが,各原人コマが2つずつ所持している特殊アクションの数々だ。特殊アクションはゲームを通して7回(原人コマごとに最大2回)までしか使用できないという制限はある代わりに,その効果はまさに“切り札”と呼ぶにふさわしい強烈なものばかり。以下にその詳細をまとめたので,チェックしてほしい。
| 特殊アクション名称 |
効果 |
| 火 |
互いに操作パネルの配置が完了した後(公開する直前),自身の周囲8マスの中から空き地を1マス選んで「火トークン」を配置する。トークンは配置されたマスと,トークンが向いている先1マスを侵入不可状態にする。侵入を試みた原人はダメージを受け,元のマスに戻される。ラウンドが終了すると火トークンが裏返され,効果範囲がトークンがあるマスだけとなる。さらにラウンドが終了すると,トークンが除外される |
| 火の玉 |
互いに操作パネルの配置が完了した後(公開する直前),自身から見て正面3マスの中から空き地を1マス選んで「火の玉トークン」を配置する。トークンが配置されたマスに侵入した原人はダメージを受け,トークンが除外される。ラウンドが終了すると火の玉トークンが裏返され,トークンが向いている方向へ1マス移動する。さらにラウンドが終了すると,トークンが除外される |
| 走る |
操作パネルで示した方向に,直進で2マス進む |
| ダブル投げ込み |
同時に2個まで棍棒を投げられる。この効果で投げる棍棒は,それぞれ別の場所に配置してもよい(同じ場所に重ねてもよい) |
| 一撃必殺 |
より強い力で棍棒を投げられる。この特殊アクションを使用した原人コマの棍棒に当たった敵の原人コマは即座に除外される |
| 治療 |
自分を含む周囲8マスの原人コマを1つ選び,たんこぶピンを除去する。この効果はラウンド終了後に行われ,この効果で本来除外されるはずだった原人が生き残る場合もある |
| プテラノドンを呼ぶ |
この能力を持つ原人から見て,横3マスの中から1つに「プテラノドントークン」を配置する。配置したラウンドでは,プテラノドントークンを中心に横3マス,前後に無限の範囲から2マスまで同時に棍棒を投げられる。この際,岩山による射程の制限は無視する |
| 建築士 |
沼を一直線に飛び越えて移動できる |
特殊アクションは各キャラクターが2つまで持っているが,1度使用した特殊アクションは2度と使用できない。また,ゲーム全体で合計7回(指定するためのリングが7個しかない)しか使えないので,どのキャラクターの能力を使うかも考えどころだ
 |
 |
ざっと1回通して遊んでみての感想だが,本作は(相手の脳内以外は)すべての情報が公開されたまま進行する&ランダム要素が皆無であるため,ゲーム全体の見通しはとても良い。にも関わらず,基本的に相手の行動を読みさえすれば相当な劣勢でも勝ちの目が残るので,特殊アクションも含めて考えると“完全な詰み”が発生しにくいのが面白いポイントだ。
ただし,岩山タイルによる遮蔽の処理,特殊アクションの処理などなど,一度に処理しなければいけない情報の量は少ないとは言い難い。また,一部の情報隠匿手段(ゲーム開始時の配置,チーム内での情報交換の制限など)がプレイヤーに委ねられている部分があるなど,ボードゲーム初心者にとっては少々ハードルが高いかもしれない。
だがそれでも,本作の“重み付けの異なる読み合いがボード上で同時発生する”というゲームシステムはなかなかに魅力的。「あそこで特殊アクションを使っていれば」とか「最初の配置はこうすべきだった」とか,驚くほどプレイ後の感想戦が盛り上がる作品だ。
2対2のチーム戦では個々のプレイヤーが考える要素が減るので「まずは分担してプレイしつつルールを覚えよう」という気持ちでチーム戦を遊び,その後に1対1で研鑽を重ねていくスタイルをオススメしたい。
独特な操作システムを使いこなして敵を殲滅! 2人専用の戦車戦ゲーム「ファイナルアクト」
続いて「ファイナルアクト」にも触れていこう。ゲームシステムはストーンデイズと通じる部分があり“秘密裏に移動先を決定する”や“すべての駒が同時に動く”といった基本的な要素は共通している。
ただしファイナルアクトは2人専用で,かつ特殊能力などが存在しないため,比較的シンプルな作りと言える。また,先に紹介したストーンデイズが2018年,ファイナルアクトは2015年の出版(原語版)ということで,どちらかと言えばファイナルアクト側が“元ネタ”ということになる。
| タイトル |
ファイナルアクト / FINAL ACT |
| 価格 |
6050円(税込) |
| メーカー |
Tyto Games |
| 発行年 |
2016年 |
| 作者 |
Sharon Katz |
| 対象年齢 |
10才~大人 |
| プレイ人数 |
2人用 |
| 所要時間 |
60分 |
戦いの舞台となるのは,7両の戦車が向かい合う砂漠地帯。ゲームボードのサイズはストーンデイズと同様の12×12で,障害物も丘陵タイル(1×2が2個,1×3が1個)に湖タイルと,基本的な部分はほぼ同様。ただし本作には
「地雷原」と呼ばれる1×3マスの特殊タイルがあり,これは“配置したプレイヤーだけが中央部に侵入できる”というルールを持っている。
これを含め,各種の障害物タイルとそれぞれ7基の戦車コマをゲームボード上に配置し,各プレイヤーに専用の操作盤を配布したところで準備完了。戦車を動かして,相手陣地の最奥まで進軍すれば勝利となる。
地雷原には中央部に矢印が描かれており,自軍だけは矢印の部分だけ自由に通行できる
 |
 |
木製コマを組み合わせて作られた戦車や砲弾のコマはけっこうな存在感があり,見ているだけでも迫力がある。また,操作盤はかなり凝った作りになっていて,重厚な厚紙にプラスチック製の“ツマミ”がコマの数だけ配置されており,触っていて気持ちが良い。昨今のボードゲームはプラスチック製のキューブやフィギュアで豪華感を出すのが主流だが,こうした工夫で臨場感を生み出しているのは面白いポイントだ。
戦車コマは,本体と砲身,砲塔の3つのパーツを組み合わせて作られているのが分かる。おおまかに全長4~5センチ程度の大きさがあり,存在感がある
 |
こちらは戦車が発する砲弾のコマ。ストーンデイズの棍棒と同じ役割のコマだが,発射した戦車が分かりやすいよう,番号が振られているのがありがたい
 |
操作盤のツマミは単にネジで止められているだけではなくバネが仕込まれていて,回すと「キリキリキリ……」という独特の音がする
 |
基本的なルールはほぼストーンデイズと同様で,操作盤で各戦車の移動内容を設定した後,公開前に攻撃するマスを指定。その後に「せーの!」で操作盤の内容をオープンし,被弾した戦車へのダメージを処理していく。
被弾した戦車は炎上状態となり,このままもう一度被弾すると大破してゲームから除外されてしまう。今回は採用しなかったが,説明書には“大破状態になると戦車がそのまま障害物になる”という特殊ルールも用意されている
 |
 |
ストーンデイズと大きく異なるのは,操作盤を使用した移動と攻撃時の射程範囲の2点。射程範囲は,手前3マスからダイヤモンド状に攻撃範囲が広がる形になっている。ただし,斜線の通らない丘陵タイルの裏側は完全に攻撃が不可能なので,ストーンデイズより地形の価値が高まっていると言えるだろう。
左が通常の攻撃範囲で,右が丘陵に登った状態での攻撃範囲。少々分かりにくいかもしれないが,先端に1マスだけ範囲が追加されている
 |
 |
丘陵の裏に隠れている場合の攻撃範囲。かなり狭いが,意外と斜めに対して“利く”シーンも多い
 |
操作盤には戦車ごとに2つのツマミがあり,上のツマミは移動先のマス,下のツマミは移動後の角度を示している。
テキストで説明するのは少し難しいが,戦車は真横へ移動することができず,その場で角度を転換することもできない。例えば,右を向きたい場合は右斜め前に移動するか,左斜め後ろに移動しなければいけない,という制限がある。
このルールがある関係で,障害物を避けて最短距離を進もうとすると進軍ルートが制限され,進軍経路の予想がかなり容易になる。プレイヤーは常に「遠回りをして回避を優先する」か「被弾覚悟で最短距離を突っ切る」という悩ましい2択に向き合うことになるワケだ。
この写真の状態を基準として考えて……
 |
移動先を「右斜め前」に設定,角度を「正面」に設定すると,角度を維持したまま斜め前に移動する
 |
 |
移動先を「右斜め前」に設定,角度を「右」に設定すると,角度を偏向しながら斜め前に移動する
 |
 |
本作には戦車個別の特殊能力は存在せず“
移動先を読んで砲撃を行い,相手の読みをかわす”という遊びに集中できる。ストーンデイズの読み合いを,よりシンプルな形で表現した作品と言えるだろう。
射程範囲の判定が複雑であるなど,2人専用ゲームの基準で考えれば難度が高めなのは間違いない。逆に言えば,2人専用でこれほどガッツリと遊べるゲームは少ないので,そういったゲームを求めている人には,ぜひオススメしたい作品だ。
��但��|����尊��但��|����贈��但��|����造��但��|����孫��但��|����造��但��|����属��但��|����造������蔵但��測�臓��但��|����造��但��|����足��但��|����造���������束 G123��但��|����造�������γ�遜��但��|����促��但��|����族��但��|����臓��但��|����村��但��|����促����������
������蔵但��測�他���������続��但��|����其��但��|����臓��但��|����臓��但��|����則G123