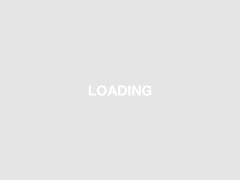イベント
[CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは
CEDEC 2010の最終日(9月2日)には,マサチューセッツ工科大学(MIT)の石井 裕教授が,「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」と題した基調講演を行った。「タンジブル・ビット」は,人間とデジタル情報,そして物理世界をシームレスに繋ぐユーザーインタフェースのことで,形のない情報に直接触れられるようにする,実体感があるものを指す。石井教授は,会場に集まったゲーム開発者に向けて,タンジブル・ビットのコンセプトや,それに関する研究を紹介。さらにタンジブル・ビットを生み出す基盤となったMITメディアラボを取り巻く“競創”の風土に言及し,そこで生き抜くための哲学を披露した。本稿では,その示唆に富んだ内容をレポートしていこう。
![画像集#001のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/001.jpg) |
![画像集#002のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/002.jpg) |
![画像集#003のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/003.jpg) |
しかし,考えていくうち,かつて石井教授が遊んだことのあるゲームには,ある意味で“人生”についてのメッセージが込められていたのではないかと思い至ったという。
実は,そのゲームとは「テトリス」だったのだが,石井教授はそこに中間管理職の悲哀が表現されていると述べる。すなわち上から降ってくるブロックは上司から次々に投げられる無茶な要求であり,下に溜まっていくブロックは部下からの突き上げというわけだ。
続けて石井教授は,日本の若者の間でラプラス(フランスの数学者/天文学者)が話題になっていると思ったら「ラブプラス」だった,という,どこまでが冗談なのか分からないエピソードなどを披露し,聴講者達を爆笑させた。
![画像集#004のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/004.jpg) |
![画像集#005のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/005.jpg) |
石井教授が最初に紹介したタンジブル・ビットのサンプルは,「PingPongPlus」と,その改良版「PingPongPlusPlus」。通常の卓球と異なるのは,ボールの動きに合わせて音楽を奏でたり,映像を表示したりする卓球台「reactive table」の存在だ。
![画像集#006のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/006.jpg) |
![画像集#007のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/007.jpg) |
石井教授は,MITで研究を進めるためのキーワードとして,「競創」を挙げ,それを説明するために「100メートル」という言葉を選択した。100メートルトラックを速く走ることは競創ではない。誰も分け入ったことのない道なき原野を切り開き,一人で全力疾走することが競創であり,MITにおける研究なのだという。
その孤独な過程の中で重要になるのが「独創」だ。その例として,石井教授は任天堂のWiiを挙げ,“身体”を動かして操作するという発想,そしてソーシャルに遊ばせるというコンセプトの点から,「ヒューマンインターフェースに革命を起こした」と絶賛した。
![画像集#008のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/008.jpg) |
![画像集#009のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/009.jpg) |
残念ながら宮沢賢治のリアリティは,石井教授がかつて購入した活字の詩集には表現され得ない。しかしその詩集には,石井教授が読み込んだ結果,多くの汚れが付着している。これもまた“身体”の“痕跡”といえるだろう。
石井教授は,ここに新しい課題があるのではないかと指摘する。モノの作り手,あるいは受け手がどういう思いを抱いていたのか,“身体”の“痕跡”から“想像”することは,短歌や俳句のように限られた字数の文章からリアリティを読み取り,感動することによく似ていると,石井教授は述べる。そして逆に,昨今流行の汚れが残らないような技術が施されたモノでは,感動を呼び起こすことはできないかもしれないと続けた。
そうした考えのもとにMITで研究を進めたと紹介されたのが,「musicBottles」(音楽の小瓶)だ。これはフタがインターフェイスになっており,その開け閉めに応じて,ガラスのボトルが音楽を奏でるというもの。研究や実演を続ける中で落として壊れたボトルもあったそうで,やり直しがきかない,リブートできないという側面を持っている。
musicBottlesはそれ自体,大変優れた技術であり,各方面で高い評価を受けたが,ここで重要なのはその発端となったアイデアだ。その原点は,石井教授が,母親へのプレゼントにしようと考えていた「天気予報の小瓶」にある。これは朝起きて小瓶のフタを開けたときに鳴る音によってその日の天気が分かるというもので,料理をするときに醤油の瓶を開けると周囲に醤油の香りが漂う,母親をイメージさせる事象に基づいたアイデアだったという。すなわち,母親の“身体”の“痕跡”がヒントになっていたのだ。
![画像集#010のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/010.jpg) |
![画像集#011のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/011.jpg) |
さらに「Illuminating Clay」 と,その発展形「SandScape」が紹介された。これは粘土や砂のモデルを使った景観デザインシステムで,実際に手を使ってモデルを変形させると,その結果が即座に計算結果に反映されるというもの。リアルタイム性もそうだが,グループで景観デザインを進めることが可能となるという大きなメリットを持つ。また何よりも大きな特徴は,かつて多くの人が経験したであろう,粘土遊びや砂遊びを思い起こさせる“身体”性だという。
石井教授は,従来の“フィジカル(身体的)”なデザインフィギュアと,“デジタル”のデータそれぞれがもたらす強みの双方を共存させるため,こうした試みを行っている。さらに,“フィジカル”と“デジタル”を言い替えることで,「art & science」と表現できるようなメディアの研究を進めているのだと付け加えた。
![画像集#012のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/012.jpg) |
![画像集#013のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/013.jpg) |
ここで石井教授は,我々を取り巻く環境の“変化”に言及する。石井教授は,今どこにいて,これからどこに向かっていくのかを早期に見抜く能力が必要であると述べ,そのメタファーとして生態系とエコロジーを挙げた。
続けて石井教授は,デジタルの世界でもエコロジーが進んでいると指摘。それはいわゆるクラウドの概念であり,「Evernote」や「Twitter」などを介し,世界中で膨大なデータがやり取りされていることに触れた。
![画像集#014のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/014.jpg) |
![画像集#015のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/015.jpg) |
そうした“変化”を踏まえることが,ゲームにとって極めて重要なことであると,石井教授は述べる。すでに起きたものは過去であり,むしろ次にどういう“変化”を起こすか。それは“流水”のようなものであり,うねり,蛇行した先には必ず“循環”がある。その中で自分がどうして行くか,経験や体験をどうコンテンツに反映させるかを考えなければならない。
また“変化”の波に揉まれる中では,不動の部分,つまり“理念”が重要となる。技術やアプリケーションは毎年のように新しいものと入れ替わっていくが,中心となる“理念”は100年経っても変化しないものでなければならない,と石井教授は述べる。そして“理念”と,実際に顧客が喜ぶモノ/技術を結ぶ“稲妻”のようなアイデアを求めて,常にアンテナを張っていなければならないとまとめた。
![画像集#016のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/016.jpg) |
![画像集#017のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/017.jpg) |
そして話題は“タンジブル”──“存在”に移行する。例えばWeb上で必要となるパスワードは曖昧な“存在”だが,リアルな鍵なら手で触ることで“存在”を確かめられる。その分かりやすさ,リアリティが“タンジブル”だ。
ゲーム開発者は,ただ存在するだけでは頭の中のものを他人に伝えられない。そこでペンや楽器,PCを使って,アイデアをテキストや絵,音楽に変えて伝えることとなる。石井教授は,その“手を使う”ことが重要なのだと指摘する。そしてソロバンを引き合いに出して,実際に“身体”を動かし,物理空間の中で計算結果を出していくこと──つまりインタラクティブな体験をすることが大事なのだと述べた。
![画像集#018のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/018.jpg) |
![画像集#019のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/019.jpg) |
ここで石井教授は,現在のコンピュータに言及し,そのインプットからアウトプットまでの計算過程は,人間ではデコードできないと述べる。すなわち,上記のようなインタラクティブな体験は不可能になってしまう。
そこでソロバンの計算過程,あるいはそのほかの使い方のように,人間でもデコード可能なユーザーインタフェースをコンピュータに用意しなければならないのだが,そこに登場するのが石井教授の提唱するタンジブル・ビットというわけである。
![画像集#020のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/020.jpg) |
![画像集#021のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/021.jpg) |
続いて,離れていてもお互いに触れ合っているかのような感覚を得られる装置「Haptic Interpersonal Communication Midium」と,モノを動かすことで別々の部屋にいる二人が同じ部屋にいるかのようなリアリティをもたらす「Ghostly Presence」をはじめ,さまざまな研究が紹介された。
![画像集#022のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/022.jpg) |
![画像集#023のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/023.jpg) |
![画像集#024のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/024.jpg) |
![画像集#025のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/025.jpg) |
![画像集#026のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/026.jpg) |
![画像集#027のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/027.jpg) |
さらに,筆のようなデバイスを用いて触れたものの色でそのまま絵が描けるグラフィックスツール「I/O brush」,光を出すだけでなく吸収もする双方向の電球「I/O Bulb」と,それを応用して建造物の日照などに関する影響を検証する「Urp」が紹介された。また,映画「マイノリティ・リポート」に登場するジェスチャー認識インターフェイスの原案となった「g-speak」も登場。
こうしたツールなどの要素をゲームに落し込むのは大変な試みだが,石井教授は実現可能となるよう,研究を続けているという。そして「The future is here. It's just not evenly distributed.(未来はここにある。ただ,均等に割り振られていないだけだ)」という,SF作家ウィリアム・ギブスンの言葉を引用し,まるでSF映画に出てくる絵空事のようなものを現実化するビジョン──“理念”を抱くことが重要であると,会場に集まったゲーム開発者に呼びかけた。
![画像集#028のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/028.jpg) |
![画像集#029のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/029.jpg) |
![画像集#030のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/030.jpg) |
![画像集#031のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/031.jpg) |
![画像集#032のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/032.jpg) |
![画像集#033のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/033.jpg) |
基調講演の終盤,石井教授は未来に向けて,クリエイティビティたる「独創」,異なる分野とのコラボレーションを示す「協創」,そして上記の「競創」の三つの原理が重要になると述べた。
続けて自らの哲学である「出過ぎた杭は誰も打てない」という言葉を紹介し,さらに出過ぎたことをするための「燃料」を,次々に挙げた。
出過ぎるためには,知的な「飢餓感」を抱くこと。そして「屈辱」を受けたときにはその経験をポジティブに変換して,いつか見返してやると思うこと──すなわち「誇り」を持つこと。「情念」を持ち,自分のやっていることに喜びや生きがいを感じること。「How」ではなく,「Why?」という「問い」を持つこと。そして,「Why?」を持って他者と接するためには,自分自身にも「哲学」レベルのアプローチが必要になること。ゲームには直接関係がないのだが,始めから終わりまで色々と示唆に富んだ講演であった。
![画像集#034のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/034.jpg) |
![画像集#035のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/035.jpg) |
![画像集#036のサムネイル/ [CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/036.jpg) |
- この記事のURL:







![[CEDEC 2010]石井 裕教授が,基調講演「Defying Gravity: The Art of Tangible Bits 重力に抗して:タンジブル・ビット」で披露したMITメディアラボの文化風土とは](/games/105/G010549/20100902091/TN/038.jpg)