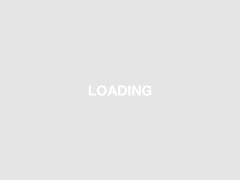[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)
![画像集#002のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/002.jpg) |
Intel,AMD,NVIDIAといった,PC業界で著名なハードウェアメーカーがブースを構えるのも,基本的には本セクションである。2010年8月4日の記事でお伝えしたEmerging Technologies(E-TECH)展示セクションは,SIGGRAPHの審査機構に技術論文を提出し,審査を受けてパスしなければブースを構えることすらできないうえ,そのスペースも有限。一方,一般展示セクションなら,参加代金さえ積めば大きなブースを構えられるため,次世代技術をビジネス的かつ大々的にアピールをしたい有力企業は,こちらにブースを構える傾向にあり,だんだんと線引きも曖昧になりつつある。
ともあれ,本稿では,SIGGRAPH 2010における一般展示セクションから,AMDとNVIDIAブース様子をお届けしたい。
パッシブ型で“フル解像度”の3D立体視!?
AMDが平面/立体視両対応ディスプレイを展示
![画像集#003のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/003.jpg) |
ブース内展示の主力は,2010年春にリリースされたワークステーション向けGPU/グラフィックスカードで,「ATI Radeon HD 5870」のワークステーション版にあたる,「FirePro 3D V8800」である。
ただ,ブース内展示で一般来場者の人気を集めていたのは,Planar Systems(以下,Planar)の平面視&立体視両対応ディスプレイシステム「SD2620W」だった。
![画像集#004のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/004.jpg) |
![画像集#005のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/005.jpg) |
偏光方式の立体視は,画素の半分を左目用に,もう半分を右目用に,偏光方向を変えて表示するのが一般的である。そのため,得られる立体像の解像度が,液晶パネルの持つ解像度の半分になってしまうという弱点があったのだが,Planarのソリューションは,「偏光方式を採用しながら,フル解像度の立体像が得られる」というのが特徴になっている。
![画像集#006のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/006.jpg) |
| 立体視利用時のセッティング |
![画像集#007のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/007.jpg) |
| ハーフミラーを上げれば,明るい,というか通常輝度での平面視が可能 |
左目用と右目用に1枚ずつ液晶パネルを2枚用い,ハーフミラーで合成してユーザーに見せるというアプローチをとっているのである。
具体的には,ユーザーの視線延長線上に液晶パネルを1枚用意しつつ,“その上”にもう1枚,天板というか,庇(ひさし)よろしく設置。これらを,視線方向に対して斜めに配置したハーフミラー越しに見ることで,左目用の映像(天板側)と右目用の映像(視線方向側)をフル解像度で同時に得るという設計になっている。
ハーフミラーには「入射した光の半分を反射し,半分を透過する」という特性がある。そのため,2枚の液晶パネルが表示する,それぞれ偏向方向の異なる映像を,同一プレーン(=平面)上に合成できるというわけなのだ。SD2620Wでは,解像度1920×1200ドットの26インチパネル2枚が用いられていた。
2D平面表示を行う場合は,上側にある液晶パネルの表示を消すだけでOK。明るさを重視したい場合は,ハーフミラーを天板方向に跳ね上げるという動作でも,平面表示に切り替えられる。2枚の液晶パネルに同一映像を表示することでも2D表示は行えるものの,「視線のズレで映像がぶれて見えることがある」という理由から推奨されていない。
本方式の利点は,1枚の液晶パネルで左目用の表示と右目用の表示とを切り替えるフレームシーケンシャル方式と異なり,フリッカー(≒チラツキ,明滅)が起こらないこと。2枚の液晶パネルそれぞれが,左右の目それぞれに向けた映像を表示し続けているため,フリッカーが原理的に起こりえないのだ。この「フリッカーフリーである」という点は,平面視と立体視を切り替えながら長時間ディスプレイを見ることになるデザイナーやアーティストにとって,「疲れにくい」という点で大きなメリットになるはずである。
![画像集#008のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/008.jpg) |
| 正面からSD2620Wを見たところ。立体視時はこんな感じに,ハーフミラー越しに画面を見ることとなる |
![画像集#009のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/009.jpg) |
| 上の状態からあえてしゃがんで,下から仰ぐように撮影。天板方向にもう一枚の液晶パネルがあることが分かる。手前にせり出しているのがハーフミラーだ |
![画像集#010のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/010.jpg) |
ちなみに気になる参考価格は,展示されていたSD2620で7500ドル。22インチで1920×1080ドット解像度の「SD2220W」が5000ドル,1280×1024ドット解像度の「SD1710」で3500ドルとのことだ。
Fermiベースの新型Quadroとプロ仕様の3D Vision,
そして“操り人形システム”をアピールするNVIDIA
![画像集#011のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/011.jpg) |
| NVIDIAブースの様子。Quadro Fermiというバナーがそこら中に貼られていた |
![画像集#012のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/012.jpg) |
| お隣はNVIDIA陣営のPNY Technologies。同社はQuadro 5000シリーズの実機を展示していた |
新世代Quadroは,Fermiアーキテクチャをベースにした初のワークステーション向けGPUということで大々的にプッシュされており,ブースでは「Quadro Fermi」というバナーがそこかしこで目に留まるという状況。Quadroの従来製品はQuadro FX 5800/4800/3800シリーズで,製品型番的に少々分かりづらいため,“Fermiブランド”を前面に出したプロモーションを行っているのだろう。
![画像集#013のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/013.jpg) |
![画像集#014のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/014.jpg) |
![画像集#015のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/015.jpg) |
このほか,NVIDIAブースにあった展示で人気を集めていたのは,セサミストリートなどで知られる故Jim Henson(ジム・ヘンソン)氏が設立したThe Jim Henson Company(以下,Hensonスタジオ)とのコラボレーションだ。
![画像集#017のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/017.jpg) |
Digital Puppetとは,アニマトロニクス技術などを,CGキャラクターのアニメーションに応用するもの。これを活用すれば,モーションキャプチャーとは異なるアプローチで,リアルタイムにCGキャラクターに演技をさせることができるようになる。
HensonスタジオのDigital Puppetは,左右両足分のフットペダル2基と,左右の手となる5本指トリガー2基,腕の動きを入力できるアームモーショントラッカーなどからなる装置を操作すれば,そのまま生放送が可能なクオリティの演技をCGキャラクターに付与できるというのがウリ。セサミストリートやマペットショーで知られる人形達の演技をそのままCGキャラクターに応用できる技術こそが,Digital Puppetなのだ。
![画像集#018のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/018.jpg) |
![画像集#019のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/019.jpg) |
Digital Puppetでは,先ほど述べたコントローラの1つ1つに,対応する“演技パーツ”を仕込んでおいて,実際の演技にあたっては,それらをショートカットキー的に起動させていく。
もちろん,アームモーショントラッカーなどは,CGキャラクターの腕の動きに対応するため,この部分はモーションキャプチャーといえなくもない。ただ,5本指トリガーは,指の動きを付けるものではなく,笑顔や怒った顔,口のさまざまな動きが割り当てられているのだ。フットペダルも,足の動きのモーションキャプチャーではなく,歩くとか,ジャンプとかいった動きが割り当てられている。
![画像集#020のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/020.jpg) |
![画像集#021のサムネイル/[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/021.jpg) |
NVIDIAは,このシステムのハードウェアとソフトウェアの両面で開発協力を行ったとのことで,それゆえ,NVIDIAのブースでの展示となった次第なのだとか。
このDigital Puppetシステムは,「Henson Digital Puppetry Studio」として,操り人形師派遣込みのソリューションサービスとして提供されているという。各種イベントでのライブデモや,テレビ番組内におけるCGマスコットキャラクターとのインタラクション,テーマパークにおける来場者とのインタラクティブプレゼンテーションなどなど,採用実績がいくつもあるとのことだ。
ちなみに,東京ディズニーシーのアトラクションで,CGキャラクターの亀とおしゃべりが楽しめる「タートル・トーク」は,このDigital Puppet技術によるものである。
後編となる第2回は,プロシージャル技術を使った都市生成エンジンや,キヤノンのミックスド・リアリティ(複合現実)技術展示についてレポートしたい。
- この記事のURL:
�坦其臓臓則G123









![[SIGGRAPH]パッシブ型でフル解像度の3D立体視や“CG操り人形”システムに注目。一般展示セクションレポート(1)](/games/116/G011649/20100809053/TN/001.gif)