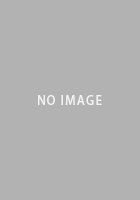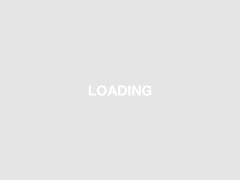イベント
バーチャルリアリティがもたらすコンテンツの可能性や収益化について,SCEの吉田修平氏らがトークを交わした「黒川塾(二十六)」聴講レポート
 |
 |
今回のテーマは,「バーチャルリアリティの未来へ 2」。バーチャルリアリティ(VR)をテーマとした2014年11月開催の黒川塾(二十壱)以降,Oculus VRのVR対応ヘッドマウントディスプレイ「Rift」製品版が2016年第1四半期に発売されることが発表されたり,E3 2015にてソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)がVR対応ヘッドマウントディスプレイ「Project Morpheus」(開発コードネーム)向けの多彩なコンテンツを公開したりと,一層の盛り上がりを見せているVR界隈について,以下のゲスト4名がトークを繰り広げた。
 |
 |
 |
 |
最初の話題は,藤山氏が演出面でVRコンテンツに関わっていることについてだ。ほかにあまり例のない立ち位置だが,藤山氏はVR界隈の現状を「先端を行きすぎて,技術に対してアンテナの高い人達ばかりが集まっている状態」とし,「自分のような演出に特化した人間が歯車のひとつとして加われば,コンテンツの魅力を増すことができるかもしれないと考えた」と説明する。
とくに手妻師としての経験から,「観客が退屈しているのではないか」ということに配慮しており,「人がどこに“現実らしさ”を感じるかを見極め,それをデフォルメし,現実を超えた演出を目標としている」という。
吉田氏は,こうしたアプローチを,自身がVRコンテンツのキモとして口にする「いかにうまく騙すか」という言葉と合致しているとし,同じく藤山氏が演出を手がけているジェットコースター体験コンテンツ「Urban Coaster」について「うまく騙せている。実際に体験すると驚きますよ」とコメント。また久保田氏は,VRテーマパークなど極めて大規模な事例を除くと,藤山氏のようなアプローチで演出に力を入れているVRコンテンツは,ほとんどないと話していた。
続いての話題は,Oculus VRの創設者であるパルマー・ラッキー氏が,E3 2015で出展された日本のVRコンテンツに対して先日コメントした件について。
その内容は,「サマーレッスン」のストーリーやプロットがシンプルであることや,「SEGA feat. HATSUNE MIKU Project: VR Tech DEMO」(関連記事)がほかの初音ミクを使ったVRコンテンツと比較して目新しいものではないことを指摘するという,少々厳しいものだった。
しかしパルマー氏がわざわざ日本の開発者が集うコミュニティにコメントを投稿したこと,そしてわざわざ日本語訳を付けていることから,久保田氏は「日本のコンテンツおよび開発者に対する高い期待の表れなのではないか」と分析していた。
その一方で吉田氏は,あるインタビューで,2014年当初は最先端だった日本のVRコンテンツ開発が,2015年に入って海外に逆転され差を付けられているのではないかと感想を述べていた。その理由として,海外では投資家が多額の資金を提供して開発者が斬新なものを作りやすい環境になっているのに対し,日本は資金面であまり進展がないことを挙げている。
このコメントについて吉田氏は,「お金になることが見えてきたので,海外では資金を提供する投資家が増えているというだけで,それはVRに限らず,モバイルゲームが台頭したときなども同じです」と改めて説明し,日本の現状については,「たとえば(海外より遅れていると言われる)インディーゲームでは,日本でも良いタイトルがそろい始めており,市場の形成が見えてきました。VRではもう少し早い動きがあるのではないかと期待しています」と述べた。
関連して久保田氏は,視線追跡型VR用ヘッドマウントディスプレイ「FOVE」など中小規模のプロジェクトに対し,短期間に集中して投資する海外の事例などを紹介。また下田氏は,Unreal Engine 4で作られたコンテンツに対し,最大5万ドルの資金援助をするEpic Gamesのコンテンツ開発援助プログラム「UNREAL DEV GRANT」を紹介した。
ちなみに,現在のVRコンテンツ開発では,主にUnityまたはUnreal Engine 4のいずれかが採用されており,下田氏によると,とくにUnreal Engine 4は企業による事例が増えているとのこと。これはゲームメーカーに限った話ではなく,さまざまな企業や商品の広報活動用VRコンテンツに採用事例があるという。
 |
しかし,日本における資金面の環境が整わないことをいくら論じても,話は進展しない。そこで重要になるのが,コンテンツの収益化であると藤山氏。藤山氏は,コンテンツを収益化する──つまり,そのコンテンツを他者に売り込むにあたって,「回転率」と「カスタマイズ性」がポイントになるとする。
まず回転率を求めるには,コンテンツの体験そのものに掛かる時間と,準備や説明,人の入れ替え,トラブル対応などのオペレーションに掛かる時間を正確に把握する必要があるとのことだ。
とくにVRコンテンツは,同時に複数の人が体験できる絵画や映画などと異なり,1回につき一人しか体験できないため,1回で3分の時間が必要となると1時間で20人しか体験できない。したがって回転率を上げるには,複数の装置を用意して,多人数が同時に体験できるようにすることが重要となる。
また多人数参加型のVRコンテンツの場合,「進撃の巨人展」に出展された「360°体感シアター “哮”」や,「ロートデジアイ 初音ミク VR Special LIVE」のような,多人数ならではの魅力を盛り込むことも必要となる。久保田氏によると,実際に日本では,こうした多人数参加型VRコンテンツが多く見られるという。一方,欧米では個人的な体験を重視する傾向にあるそうだ。
加えて,コンテンツそのものや説明を最適化することも重要となる。たとえば,諸々ひっくるめて3分掛かるコンテンツと同じ魅力を1分で提供できれば,それだけ回転率が上がるわけだ。そのため藤山氏は,コンテンツの内容や説明のセリフに無駄な部分がないか,日々チェックし,洗練を心がけているという。
またカスタマイズ性に関しては,たとえば「Hashilus」ではスタート地点とゴール地点で任意の画像を表示できるようにしている。特別な改変を施さなくとも,この画像をテレビ番組のロゴにするだけで,その番組専用のカスタマイズができてしまうというわけだ。結果として,さまざまな番組で採用されやすくなり,それだけ高い収益が期待できるという。
藤山氏は,VRコンテンツを企画開発するときに,こうした収益化に関する部分を織り込むと,これまでとは違ったアイデアや楽しみ方が生まれてくるのではないかとする。また藤山氏の手がけるVRコンテンツはアーケードゲームのようなものを考えているとのこと。つまり,特定の会場に出向き,スタッフによってきちんとセッティングされた場──いわば匠の手によって作られた場で体験するもの,ということである。
一方,下田氏は,日本では多人数参加型で短時間で楽しめるアトラクションのようなVRコンテンツが発展し,海外では個人的な体験を長時間楽しむようなVRコンテンツが発展していることにより,両者にギャップが生じ始めていることに危惧を覚えていると発言する。この意見に対して吉田氏は,大手ゲームメーカーでプロとしてゲームを作っている人達にはさまざまななノウハウの蓄積があるので,いざギャップに直面しても比較的容易に乗り越えられるのではないかと答えた。
その大手ゲームメーカーがVRコンテンツに乗り出した事例として吉田氏が挙げたのは,カプコンのホラーVRデモ「KITCHEN」だ。
E3 2015ではブースから体験者の悲鳴が頻繁に聞こえるほどの仕上がりだったとのことで,吉田氏は「以前から研究を進めていたのかもしれませんが,大手メーカーはいざ着手してしまえば,そこから完成までは非常に早いと感じました」と評していた。
 |
以上をまとめて,黒川氏は,エンターテイメントに限らず,戦場や難民キャンプなど,通常では経験できないことを,あたかもそこにあるかのように体験可能にしたのがVRであり,そこには人々の価値観を変える力があると話す。
一方で,VRの普及を牽引するのは,やはりエンターテイメントにほかならないとし,吉田氏もProject MorpheusやRiftの製品化が見えてきたことにより,ようやくその準備が整ったのではないかと話していた。
しかしVRが普及することにより,たとえば一時期騒がれた「ネトゲ廃人」のように,VRの世界にハマり込んでしまい,リアル社会に戻れなくなる人も出てくるのではないだろうかという懸念もある。
この疑問に対して藤山氏は,人々がゲームにハマるのは射幸心を煽る仕組みや,コミュニティの部分であり,VR自体が提供する臨場感や没入感とはあまり関係がないのではないかと回答した。
かつて自身がネトゲ廃人だったという久保田氏は,藤山氏に同意しつつも,今後,多人数が同時に接続するVRコンテンツが登場し,そこに協力/対戦要素やコミュニティ要素などが加わったとき,従来のオンラインゲーム以上にハマる人は出てくるかもしれないと述べていた。
一方,下田氏は,ただでさえコンシューマゲーム機のパッケージソフトが思うように売れなくなっている昨今,そうした高クオリティのVRコンテンツにどのくらい需要はあるのか,またその開発予算をどのように確保すればいいのかといった,ビジネス面での課題を提示していた。
このように今後の展開に大きな期待が寄せられる半面,従来のエンターテイメントが残した前例から,すでにさまざまな課題が出てくることも考えられるVR。本稿では,トークの終盤に吉田氏が語った「まずは,人々がハマってしまうほど魅力的なVRコンテンツを作ること。いろいろな心配は,そういうものが出てきてからすればいいんじゃないでしょうか」との言葉を持って,締めとしよう。
 |
- 関連タイトル:
 Rift
Rift
- 関連タイトル:

 PlayStation VR本体
PlayStation VR本体
- この記事のURL: