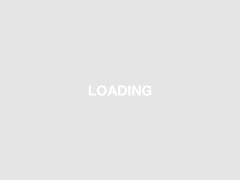KADOKAWAから発売中のトレーディングカードゲーム
「ドレッドノート」の世界観を深く掘り下げていく連載企画
「Dreadnought Episodes」の第2回をお届けする。今回物語に登場するのは,赤の組織「八幡学園都市」から
旭レイジ,
恵比寿ユイ,そして青の組織「I2CO」から
アリス・フィフティベルの3名のキャラクターだ。
八幡学園に通う高校生であるレイジとユイ,そしてアメリカから八幡学園都市にやってきた神醒術の天才,アリス。この3人の物語は,これからどのように交わり,あるいは分かれていくのか。ぜひその目で確かめてほしい。
 |
旭レイジ 昼行燈のサボタージュ #1
面倒くさい。
旭レイジは常々そう思っている。だいたいぜんぶに対して。
勉強は嫌いだ。運動もダルい。だからよくサボる。けど、サボりすぎると教師に目をつけられるからそれも面倒くさい。不良という、太古に存在したらしい絶滅種みたいにエネルギッシュには生きられない。
たとえば宿題。いちおう提出はする。ろくに問題文さえ見ずに回答を書いたものを。当然、中身は間違いだらけだが「ぼくなりに頑張ったんだけど間違いました、馬鹿でごめんなさい」という雰囲気だけは出しておくよう心がける。そうすれば教師は、怒りよりも呆れや哀れみの目で見てくれる場合が多いので、未提出で怒られるより楽だ(クラスメイトの中には、友人に写させてもらう、というやつもいるが、丁寧に転写するよりも適当に書いた方が時間もカロリーもかからないと思う)。
レイジはいつだって、ローコストな日常を愛している。省エネ万歳。
今日もいつもどおり、無難に授業をこなして一日を終える。終業の礼をするやいなやざわつく教室。その中で担任の久保田が声をはり上げた。レイジに、ついてこい、との呼び出しだった。
突然のことに、予想していなかったレイジは一瞬目を丸くした。が、すぐ素直に頷いた。驚くのも質問するのも面倒くさい。
それに呼び出しの理由はなんとなく想像がついた。先日の誘拐事件に関することだろう。レイジは机の上にあった荷物を鞄につめこむと、久保田につづいて教室を出た。
八幡学園都市は、関西の丘陵地帯にある「神醒術の聖地」だ。
世界中の神醒術士が憧れる場所で、数多くの学生と研究者が暮らしていて、その土地は3つの市にまたがるほど広い。
エリアは研究所区画と学園区画に分かれているが、学園区画の校舎も研究所としての側面を持つ。
研究内容や学園の授業内容など内部の詳細情報は、外部にほぼ漏れないため、一般市民からは「有名だが何が行われているのか不明の、得体のしれない場所」と認識されている。たまにテレビで「八幡学園都市の研究チームが新しい技術を開発」という風な、話題性のあるニュースが流れるだけだ。中で暮らしているレイジでさえ、正直、この都市については知らない情報が多い。
学園の敷地も一般的なものより遥かにでかいせいで、詳細を把握しきれない。幼等部(幼稚部)、小等部(初等部)、中等部、高等部、大等部(大学部)……とあり,それぞれの園舎や校舎もひとつじゃないし、授業で使わない特別な施設だってある。
久保田に案内された先は、高等部に1年以上通っているレイジですら、存在を知らなかった部屋だ。久保田は部屋には入らないつもりらしく、レイジの荷物をひとまず預かって、背中を軽く押しただけだった。
室内はまっしろな壁と床。奥の小窓から光が入っている。部屋の真ん中に、重厚感のある木目調の低いテーブル。そのテーブルを手前と奥から挟むように、革張りの二人掛けソファがそれぞれ置いてある。
先客がひとりいた。
奥のソファに、黒い警官服の五〇代くらいの男が座っている。耳にかからない程度の短髪には白色が混じり、顔には皺がかなり入っているが、萎れたというよりは熟した、という言葉が似合う印象だった。
「やあ、こんにちは。旭レイジくんだね? 八幡学園都市署、神醒術犯罪対策部の天遊琳(てんゆうりん)です」
と、男は立ち上がって一礼した。
「警察?」
予想できてはいた。でも、じっさいに校内で目にすると現実味がなくて、ついレイジはわかりきっていることを尋ねた。わざわざ出向いてくるとは、ずいぶん大ごとになっているなと思う。
天遊琳警部は微笑んで、握手を求めた。顔つきは厳格そうなのに、どことなく内面の穏やかさも滲み出ている人だ。
握手を終えて、天遊琳警部は向かいのソファを、どうぞ、と示す。誘われるがまま腰を下ろす。クッションが予想よりも深く沈みこんだせいで、うお、と小さく声が漏れた。
恥ずかしくて天遊琳警部をうかがったが、彼はその声に反応はせず、微笑のまま続けた。
「忙しいところを学校まで訪ねてしまってごめんね。もうわかっているかもしれないが、君が先日遭った誘拐事件について質問させてもらいたくて来たんだ」
学園の生徒が下校中に誘拐された――ひと言でまとめると、それだけの事件だ。珍しいっちゃ珍しいけど、八幡学園都市には色んな人間が集まっているし色んな物騒が起こりまくっているのでテレビでは些細なニュースにしかならなかった。せめてもの話題性は、犯人たちがマフィアじみた銃火器で武装していた点。それと、多少は神醒術についても知識を持っていたことくらいか。
ただ、その犯人たちはすでに警察に捕まっている。ひとまずの解決はしたはずだ。
なら、なんで警部は来たのか。
「犯人の目的が、はっきりしなくてね。レイジくん、もう一度、要点を整理させてほしい――我々が連絡を受けて駆けつけた時点で、犯人は無力化されていた。それをやったのは君だ。間違いないね?」
当時、レイジは誘拐犯を神醒術で倒した。それからスマートフォンで警察を呼んだ。だから、だいたいの説明は現場で済ませてある。あのとき駆けつけた警察は天遊琳警部ではなかったけれど、情報は共有されているのだろう。
「はい。間違いありません」
「なぜ攻撃したのかな?」
「犯人が、他の誰かにも危害を加える的なことを言ってたからです」
「うん。君は犯人同士の会話の流れから、君以外にも神醒術士が狙われていると知った。それで正義感から、神醒術を使って犯人たちを攻撃し、無力化した」
「はい」
ちょっと嘘だった。本当は正義感からじゃない。神醒術士を理由にした犯罪が起きると「神醒術士は厄介ごとの元凶だ」という声が強まりかねないと思ったからだ。考えの古い連中は、今でもそういう傾向にあり、神醒術士を責める口実を求めている。
誘拐犯への反抗は、気持ちよくダラダラ生活を続けるための、あくまで利己的な行動だったけれど、それを正直にバラすメリットもなさそうなので黙っておく。
「まだ若いのに、立派だね」
「いえいえ、そんな」
「さすがは若き優秀な神醒術士だ。おじさんには、そういう力がないから羨ましいよ」
意外だった。神醒術士の対策を担当している警部が、神醒術を扱えないのは珍しいんじゃないだろうか。警察について詳しくないのでわからないけれど、たぶん。まぁレイジが口を挟むことではない。
「――他には?」と天遊琳警部が首を軽く傾げる。「なにか、犯人は言ってたかな」
「別の武装チームがまだあるっぽいです」そういう会話を、誘拐されている最中に聞いていた。「だから誘拐事件は、まだ起こる危険があるんじゃないすかね。これも前に話したことですけど」
「うん、そうだね。だがそれについては私から君に、新しい報告がある」
「え?」
「もうひと組、同じく誘拐を企てていた武装集団が逮捕された。奴らのグループはこれで全滅だ」
へえ、とレイジは思わず感心の声を漏らす。漏らしてから、ちょっと偉そうな反応だったかもなと反省する。でも、それくらいに意外だった。レイジが襲われてから48時間も経っていない。武装グループを見つけるのも逮捕するのも、予想よりずっと早い。
「もう安心ってことですか」
「もちろん言いきれはしない。だがまぁ、わかっていた脅威に関しては取り除かれた、というのが現状の事実だ」
「さすがは八幡学園都市の警察。優秀ですね」
「いや、今回も君のときと同じく、我々の手柄とは言いづらい逮捕ではあったよ。やはり神醒術士という人種は、こと戦闘において一般的な警官よりは腕が立つのだろう」
神醒術士――口ぶりからしてレイジと同じように、被害者が犯人を倒してしまったパターンだろうか? 少し気になったが、個人的には関係ないので適当に流しておく。それよりもパッパと、この取り調べを終えて帰りたかった。
それから20分ほど、天遊琳警部と話した。
新しい話題は他になかった。レイジがまだしも興味のあった「誘拐犯の目的」はさっぱりわからないままらしい。そのへんについて誘拐犯は吐かないのだという。 話の終わりに、レイジはいちおうの体裁として謝っておく。「すみません、目新しい情報を提供できなくて」
いいんだよ、と天遊琳警部はまた穏やかに笑った。
「私が今回この学校を訪ねた一番の目的は、君が事件後のショックで参っていないかを確認することだった。では、今後なにか思いだすことがあったら、いつでも連絡をください」
なんて言い残して、警部は部屋を出た。
レイジは、前半は社交辞令だろ、と内心で苦笑したが同時に、悪い人ではないのだろうなと警部に好感も持った。あのおっさんなら、また事情聴取につきあってやってもいい。
天遊琳警部との話を終えたころには夕暮れどきだった。白い塗装の部屋は、窓から差し込む光でオレンジに染まっている。
部屋から出ると担任の久保田が待っていた。レイジの荷物を差し出して、おつかれさん、気をつけて帰れよ、と言った。レイジは礼を返して荷物を受け取り、校舎を出る。
吹奏楽部の演奏と、野球部のかけ声が焼けた空にのぼってゆく。部活動生はまだ元気に練習しているようだが、帰宅部はとっくに帰っているべき時間だ。家でダラダラと過ごすつもりが予定外に体力をつかいすぎた。さっさと帰ってダレなければ、とレイジはため息まじりに校門を出た。
しかしそこで、不意打ちのように「レイジ」と声をかけられた。
振り返ると、校門の塀に、長い黒髪の少女が背中を預けていた。少女は、にやりと意地悪く笑うと言った。
「今日ひま? あなたにとって、ためになる話があるんだけど」
恵比寿ユイ。同じクラスの委員長だ。
やっかいな奴に捕まった。
今日は厄日かよ、とレイジは頬を引き攣らせた。
恵比寿ユイ よすがのレスポンス #1
恵比寿ユイは、よく「模範生」だと言われる。成績優秀、スポーツ万能、武道にも精通しており、心技体すべてのパラメータが高い。学園では学級委員長も務めていて、教師たちや先輩、後輩からも受けがいい。
でもユイ本人としては、べつに点数稼ぎのために頑張っているわけじゃない。ただ責任感から動いているだけだ。人にはそれぞれ果たさなければならない責任がある。ユイの場合は「信頼に応えること」がそれにあたる。
そんなユイは、かわいい後輩から相談を受けたとなれば断れない。
相談の内容は、ストーカーについてだった。
最近、怪しいやつにつきまとわれているという。たしかに後輩は整った顔だちの女の子なので、悪い男に狙われてもおかしくはない。
ただ、この件にはすこしだけ不思議な点、というか懸念しなければならないことがあったので、ユイは協力者を呼ぶことにした。適任なのは、ユイが委員長を務めているクラスの同級生、旭レイジだ。
放課後、ユイは校門の塀に背中を預けて、彼の下校を待っていた。
ユイがレイジを協力者に選んだ理由はいくつかある。ユイと親交が深いからというのがひとつ。もうひとつは、単純に戦闘力の高さだ。
レイジはああ見えて、入学試験のときに、神醒術の実技を1位の成績で合格している。さらに先日の誘拐事件でも活躍した。彼は言いふらしたがる性格ではないのでニュースと噂でしか聞いていないけれど、誘拐犯を倒して怪我ひとつなく生還したらしい。神醒術士はその立場上、一般人よりも遥かに厄介事に巻き込まれやすいし、自衛のすべも知っている。とはいえ、銃を持った集団を相手に無傷というのはやはり異常だ。ストーカー事件に関わるとなると危険な目に遭うかもしれない。後輩の身も自分の身も守れる人しか誘えない。その点でレイジには安心感がある。
もっと言えば、彼自身のため、という理由もある。
入学時の実技試験、ユイは2位だった。レイジより下だ。
なのに今ではユイのほうが「模範生」として、レイジよりも優秀かのように評価され、レイジは「問題児」――劣っているかのように思われている。そもそもユイとレイジの親交が深い理由だって、ふたりが「模範生」と「問題児」というわかりやすいレッテルのせいで、授業のときによくペアを組まされるからだ。
これがユイには納得できない。
なによりも頭にくるのは、レイジ自身がこういった低い評価を「別にいいんじゃね?」と受け入れている点だ。
自分の憤りがどこからきているかはユイ自身にも上手く言えない。学級委員長だから。レイジの友人だから。あるいはもっと他の理由からか。わからないけれど、意地でもレイジに本気を出させて、彼の実力をみんなにちゃんと認めさせたい。それが自分の責任なのだと思う。
塀の端から顔を覗かせて校舎のほうを確認すると、ちょうどレイジが出てくるところだった。ユイは塀の影にささっと身を隠して思う。
――さて。私が急に声をかけたら、レイジはどんなふうに驚くだろう?
その反応ていどのことが、なぜだかずいぶんと楽しみで、ユイはひとり頬を緩めた。
アリス・フィフティベル 深窓のプライド #1
現代、神醒術は世界でもっとも価値ある技術のひとつと考えられている。
火、水、風、電気など重要なエネルギーをほぼ同一の段取りで現すことができ、リソースとして必要なのはSI素子――「情報」だけ、というのが大きな理由だろう。SI素子については各機関が研究中で不明なところが多い物質だけれど、さしあたって使用による枯渇の心配はないという。
近い将来、神醒術による「顕現」はあらゆるエネルギー産業に代わるとされる。だからこそ世界各国に神醒術組織がいくつも生まれ、それら組織の動向は人々の注目の的となっている。
アメリカを主導とする国際機構I2COは、世界最大の人員数を誇る神醒術組織だ。神醒術に関する事柄について世界的視点で見守る、という名目を持ち、神醒術の発展や問題解決のために活動している。
アリス・フィフティベルの父は、I2COで七賢者と呼ばれる最高クラスの地位にいる。
アリスにとって父は、世界でもっとも尊敬すべき人物だ。父に認められれば、それは世界でもっとも価値あることで、逆に父に見放されれば、それは世界でもっとも深い絶望だ。
だから、父が仕事の都合で渡日するさいに同行を許してくれたとき、アリスは誇らしさで震えた。仕事人間である父にとって、有用な神醒術士以外は邪魔者だ。少なくともアリスは父に「邪魔ではない」と認められたことになる。
でも、まだ安心はしきれない。アリスは自分に神醒術の才能がそれほどないと知っている。足りないぶんは努力で補わなければ、いつ父に見捨てられるかわからない。
ただ、そんな現状にもアリスは強い誇りを持たずにいられない。
わたくしはお父様に試されているんですの、と。
「お嬢さま。ご入浴のご用意ができております」
ノックにつづいてドアの向こうから聞こえた声に、アリスはゆっくりと意識を引き戻した。目頭を押さえ、ふう、と息を吐く。握っていたペンを置き、ノートを閉じる。
机の上のデジタル時計を見れば、22時すぎだ。勉強を始めてから、いつのまにか3時間も経っている。
目を休めるために、視線を窓の外に移す。タワーマンションの最上階からは、きらきらと星のように明かりを灯す、夜の街並みが見える。
アリスは現在、八幡学園都市に住んでいる。でも学園には通わず、勉強はこうして自宅で済ます。週に何度か来る家庭教師と、あとは自習で成り立たせている。
ドアの向こうから、再び声。
「集中なさっているところをお邪魔してしまい申し訳ございません。ただもう夜も遅くなってまいりましたので。それとも、まだしばらく後になさいますか?」
今、アリスは世話役の女性とのふたり暮らしだ。いちおうこの部屋の名義人は父だが、滅多に姿を見せてくれない。忙しいから仕方がない。
アリスはふりむいて返す。
「いえ、ちょうどひとくぎりつけたところですから。すぐに行きますわ」
「承知いたしました。本日はいろいろとございました。ゆっくりと汗をお流しください」
アリスが今日、物騒な男たちに尾行されていたことも父は知らない。
でも、それでいいとアリスは思っている。父の自慢の娘であることがアリスの存在意義だから。小さなアクシデントをわざわざ報告して父の邪魔をする理由はない。
自分を狙っている者たちの素性も、目的すらもアリスにはわからないけれど、どんな相手に対してであれ屈服するつもりはないし、ひとりで対応してみせるつもりだ。
すべては、父の娘として、誇らしくあるために。
そう自分を鼓舞すると、アリスはチェアから立ち上がり、めいいっぱいの伸びをした。
文/河端ジュン一

 ドレッドノート
ドレッドノート