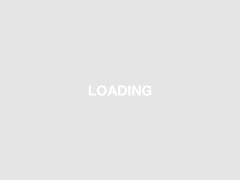イベント
コーエーテクモの襟川陽一氏やSCEJAの盛田 厚氏らが「ゲームの未来」を語った設立20周年を迎えたFOST記念講演レポート
 |
FOSTとは,「科学技術」と「人間社会や文化」との融合を促すことを目的として,1994年4月に設立された財団だ。同財団では,シミュレーション&ゲーミングの研究活動やそれらへの助成事業,優れた研究者や団体を表彰するといった活動を行っている。そして今回,今年で設立20周年を迎えたことで,それを記念して「ゲーム業界の未来」をテーマに,ゲーム業界から著名人を招いての講演会が催されたのだ。本稿でその模様をお伝えしよう。
 |
 |
 |
 |
「IPの創造と展開」を軸に成長戦略を語る襟川氏。Project Morpheusからクラウドなど,開発者としても意欲を見せる
最初に登壇したのはFOSTの理事長でもある襟川陽一氏だ。冒頭にFOST設立の経緯を話したあと,コーエーテクモホールディングスの社長という立場から「ゲームソフト会社のビジネスモデルや成長戦略」をテーマに講演がスタートした。
 |
襟川氏は,「信長の野望」から始まったコーエーテクモホールディングスの歴史を振り返りつつ,経営戦略に「IPの創造と展開」があると説明する。これは新たなIPを作り上げ,さらに多方面に展開することで成長性と収益性を確保し,発展を目指すというのがその趣旨だ。
それを構成するのが「プラットフォーム展開」「コラボレーション」「ジャンル展開」「タイアップ展開」だ。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
この四つのポイントを踏まえて襟川氏は,「ハードウェアプラットフォームやソフトウェアプラットフォームが技術的に進展しているなかで,新しい時代とともにビジネスモデルも変わります。ゲームソフトもその時代のユーザーニーズに合ったものに更新していく必要がある」と話した。
続いて氏は,ビジネスモデルの変化について言及した。携帯電話やスマートフォンの普及により,2010年を境に,ゲームを1本購入するという映画的なスタイルから,欲しいところだけ買うといったTV番組的なスタイルに変わりつつあると指摘した。
また2013年は,デジタルビジネスの売り上げが20%だったが,2014年は30%になる見込みで,今後,世界的にデジタルビジネスの売り上げが増えていくことが予想されるという。ゲームシステムもそれに適合したスタイルに変わっていくのではないかと話した。
 |
最後に襟川氏は,クリエイターであるシブサワ・コウとして,今後の展開を語った。
PlayStation Nowのようなストリーミング配信によるクラウドゲーミングは非常に意義のあるサービスで発展を期待すると話した襟川氏。ただ,自分としてはクラウドサーバーが何台もつながった,スーパーコンピュータ並の処理能力を活用したゲームを夢見ているのだという。それは,自然言語処理による理想的なUI,ビッグデータ解析によるAIの進化,そして物理シミュレーションの三つを処理しつつ,スマホや家庭用ゲーム機などと融合したものをイメージしているそうだ。
 |
そのほかに直近のものとして,来年30周年を迎える「三國志」シリーズの新タイトルを2015年に発表する予定だと述べた。ほかにも,50代,60代のシニア向けのゲーム,日本の文化に根ざした社会性のあるゲームを開発したいと意欲を見せる。
また斬新なゲームを作りたいとも話し,ソニー・コンピュータエンタテインメントが発表した「Project Morpheus」を使った新しいアイデアとして,「戦場を駆け抜ける武将」といったイメージが浮かんできているという。
さらに,2010年の東京ゲームショウで発表した,日本の歴史や文化を世界に発信するという意義も持たせたアクションRPG「Ni-OH 仁王」の開発にも力を入れていると話して,講演を締めくくった。
 |
 |
 |
20周年を迎えたプレイステーション
ネットワークの力とともに世界へと拡大する
続いて登壇したのは,SCEJAプレジデントの盛田 厚氏だ。盛田氏は「プレイステーションがもたらしてきた変化と,これから起こしていきたい方向性」について話し始めた。
 |
先日,20周年を迎えた「PlayStation」の歴史を振り返り,グラフィックスの高品質化やメディアの変化(CDからDVD,BDへ),そして流通の変化など,プレイステーションはゲーム業界に大きな影響を与えてきたと説明する。ただ,それはSCEJAの力だけでなく,ゲームを作るクリエイターのおかげだと話す。
 |
そしてここ数年,ゲームはプラットフォームやデバイスに左右されない方向に進んでいると分析。2014年9月末に,全世界で1350万台出荷を突破し,これまでにないスピードで普及しているというPS4でも,ゲームはディスクベースから,デジタルベースに変化しつつあるという。
そのなかでPS4は,ハードウェアのインストールベースのみならず,ネットワークサービスを含めたプレイステーションプラットフォームの拡大を目指していきたいと話した。
 |
PS4の世界を進化させるものとして,盛田氏が期待を寄せているものの一つが,襟川氏もあげていた「Project Morpheus」だ。これまではディスプレイの向こう側を3Dにしたり,デバイスによる操作で3Dを感じさせたりして立体感を表現してきた。しかし,次はゲームの世界に入り込んで360度の世界に没入してもらいたいと話す盛田氏。「クリエイターさんからの反響もすごく大きく,プレイステーション初期のころに近いんじゃないか」と語り,「これまでと一段違う未来のエンターテイメントを提供できる可能性がある」として,大事に育てていきたいと話した。
 |
そのほかにもシェア機能や映画配信などのサービス拡充,クラウドサービスなどを挙げ,「これまで,どこもできなかった家庭内のエンターテイメントハブを目指せるところまで来た」と盛田氏は意気込む。
 |
 |
 |
 |
最後に盛田氏は「ユーザーの想像を超えるゲームの世界を提供していきたい。エンターテイメントと呼ばれるサービスを通じて世界をつなげ,プレイステーションの世界を拡大させていきたいと思います」と,20周年の先を見据えたプレイステーションの未来を語り講演を締めくくった。
成功と失敗の繰り返しから南場氏が得た「3年後に売れるゲーム」の解答とは?
次に登壇したディ・エヌ・エー(以下,DeNA)の南場智子氏は,経営側の視点から見た,これまでのDeNAのゲーム事業展開について話し始めた。
 |
まず,これまでのDeNAが作ってきたゲームのタイプと売り上げ表のスライドを提示した。2013年で少し下がってはいるものの,基本的には右肩上がりのグラフだ。しかし,内情はなかなかスリリングな日々だったと話す。
 |
「手軽に遊べる」Flashゲームを,フィーチャーフォンに配信して大成功したDeNAだが,次はJavaだと欲をかいて作ったゲームで大コケしてしまったという。その理由は,Javaの重い動作とインフラの弱さのため「手軽に遊べる」という利点を失ってしまったのだ。
その反省をもとに,改めてブラウザゲームを研究してゲームを開発する。そこで生まれたのがあの「怪盗ロワイヤル」だ。「自分たちでもどうして成功したのか分からない」と話す南場氏だが,ここが「成功体験の落とし穴だった」と振り返る。
 |
 |
少し話がずれるが,この時期にプラットフォームをオープン化しようという話が持ち上がってきたという。それというのも,開発リソースに限界がきていたことや,自分達だけでは似たようなゲームしか出せないという弱点があったためだ。
多様なニーズに応えるためにも,利益率よりオープン化しようと決断を下した結果,自分達では出せなかったであろう,例えばカードゲームのようなスタイルもサービスできるようになり,DeNAが飛躍する大きな契機になったという。
 |
そういった感じで,調子に乗っていたところに,ユーザーがフィーチャーフォンからスマホへ流れ始めていることに気が付いたという。ここを,「ブラウザゲームに手を加えて表現を豊かにして乗り切ろうとした」ことが失敗の第一歩となる。運が悪い(?)ことにスタッフが優秀だったため,その作品がそれなりにヒットしてしまい,開発側に「ネイティブソフトよりもブラウザゲームだ」という意識ができあがってしまったそうだ。
 |
ともあれ,「FINAL FANTASY Record Keeper」の大ヒットで「ものすごく苦しみ,地獄を見て,なんとかチャンスをつかみかけている」と話すように,復活を果たしつつあるDeNAだが,多くの人員を擁しての開発に難色を示した執行役員もいたという。それは,過去に数人で「怪盗ロワイヤル」を開発し,莫大な利益を生み出した成功体験があったからだ。
そんな役員を敵に回すような形で,エグゼクティブプロデューサーが「剣を振る気持ちよさを再現できるまでの技術の蓄積と,ユーザーの期待を裏切らない面白さ」の実現にこだわったからこそ,「FINAL FANTASY Record Keeper」が生まれたと南場氏は話していた。
今後のDeNAの課題としては,プラットフォーム戦略をあげた。かつてiモードやMobageでプレイヤーを楽しませるプラットフォームを築いたが,Google PlayやApp Storeの隆盛で地位が低下してきていると分析する。
その一方で「これらはただ配信と課金決済だけを行ってるだけで,ゲームのプラットフォームとして機能していないのでは」とも話す。プラットフォームは「『値決め』など,ビジネスプランの算段を付けやすくするサポートも行うことで,投資を呼び込みやすくして,ビジネスの難度を下げる役割があるのではないか」と,その在り方を述べた。
もちろんこれは,DeNAとして頑張りたいという発言でもあるが,これからまったく新しいデバイスやコンソールに広がる可能性もあり,それを行うのが必ずしも自社でなくてもいいと話していた。
 |
 |
「結局はそのゲームが面白いかどうか」と,これまでの経緯から答えを導き出した南場氏。「モバイルゲームの未来」という講演のテーマに対しは,答えは「?」。つまり分からないと答えた南場氏。「これから3年後に流行るゲームを語る人がいたら,私は信じません」と断言する。
デバイスも通信環境もユーザーも,何もかも変わる可能性がある3年後の展開など見えるわけがないということだ。ただ,ユーザーに向き合うことがその答えかもしれないと,南場氏は話を締めくくった。
 |
 |
多くのゲームを生み出す日本がゲーム研究の後進国?
馬場教授が話す日本の「ゲーム研究の未来」とは
日本のデジタルゲーム研究の第一人者でもある東京大学大学院の馬場 章教授は,日本のゲーム研究の実情について語った。
 |
冒頭で馬場氏は,「デジタルゲームは現代の知的複合体」だとして,デジタルゲームの研究はさまざまな分野からアプローチできると語る。
その目的は「面白さ」の解明と開発だ。「なぜ面白さが発生するのか?」とは,なんとも哲学的な話に聞こえるが,それらを突き詰めることで,より面白いゲームが生まれるとしたら,ゲーマーとして歓迎したい研究だ。
 |
 |
ゲーム研究について,まずゲームリテラシーという言葉の変化から話がスタートした。
2007年以前は,アメリカの「開発者側のリテラシー」をゲームリテラシーと読んでいたが,2007年以後は日本の概念,つまりゲームをどう遊び,どうつきあっていくかがゲームリテラシーとして世界に広がったという。しかし現在では,日本におけるゲームリテラシーの研究は後進なのだという。
馬場氏はゲーム研究の光と影というスライド映し,たとえば若手の研究者が増えてもアカデミックコースが存在しない,国内の大学に学科や学部が増えても,それは少子化対策のお客さん集め的なものになると現状を語る。
 |
スライドの最後に,「日本は“また”後進」とあるのは,2012年ごろにようやくアメリカに追い付いた……と思っていたら,実はアメリカをはるかにしのぐ研究が欧州で行われていたからだ。
とくにオランダ・コペンハーゲンのIT大学にあるコンピュータゲーム研究所は,世界中に研究者を排出してゲーム研究所を作っているのだという。日本は「言葉の壁」のおかげかその影響は及んでいないが,それが後塵を拝している原因でもあるようだ。
 |
 |
これからの日本のゲーム研究について馬場氏は,社会学をベースにゲームを研究するなど,日本独自の視点で新たな研究をしていく必要があるだろうと指摘する。さらにそれらを発信する方法の確立が必要だとし,「研究の世界は2番ではダメです。1番にならなくちゃいけない」と,世界のライバルに負けないよう,競争しなくてはならないと説いた。
 |
最後に馬場氏は,ゲーム研究を通してデジタルゲームの付き合い方を考え,いつでもどこでも安心で快適なゲームプレイが行える環境を作ることがデジタルゲームの未来につながると話した。そして,やがて日本がゲーム研究の発信地の一つとして機能できるようになればと述べて,講演を締めくくった。
 |
 |
 |
これからのゲームは「コミュニティの形成と維持」が欠かせない。「リテンション」をキーワードにこれからのヒットを探る
最後に登壇したのは,KADOKAWA・DOWANGO 取締役の浜村弘一氏だ。浜村氏は「領域を超え始めたゲームコンテンツ〜ヒットへのキーワードはリテンション〜」というタイトルで,メディア側から見えてきた直近のゲームの未来について講演した。
 |
現在,スマホゲーム市場が大きくなっている一方で,世界ではPS4なども大きく伸びている。かつて「コンソールゲームなんてなくなっちゃうんじゃない?」と言われたこともあったが,これは一体どういうことなのだろうか。
データを紐解いてみると,北米,日本に関わらず,スマホだけではなくゲーム機でも遊ぶ人が少しずつ増えてきているのだという。どちらが,ではなくどっちも,とそれぞれの領域を越えて……というより,融合し始めているのだと浜村氏は語った。
かつてゲームは売りきりだったが,現在では発売後もユーザーとの関係性を継続していくような形に変化しつつある。これを浜村氏は「リテンション(retention:保持,記憶,記憶力という意味)」という言葉,ゲームに限って言うのなら「興味を喚起し続ける」というキーワードで表せるのではないかと話す。
無料アプリで遊ぶユーザーが増えてきたことにより,数倍の規模に拡大したゲーム市場。上記のように,そこから多くのユーザーは家庭用ゲームに混じり合ってきているが,それはIPについても同様だという。
家庭用ゲームからスマホに移植されたり,スマホから家庭用ゲーム機に移植されたりと,ゲームIPが混じり合い,ボーダーがなくなってきているのだ。
ダウンロード販売も存在感を大きくし,ビジネスの流れが変わりつつあるなか,マーケティングも大きく変化していると浜村氏は話す。自社だけでなく,他社のIPを取り込んだ「パズル&ドラゴンズ」を例にあげ,マメなコラボでユーザーを刺激し,どんどんユーザー数を増やしていく。昔の家庭用ゲーム機時代にはできなかった手法だが,アプリの世界では大きな力を発揮しているのだという。
このように,顧客の気持ちを離さず囲い込む「リテンション」が,「パズル&ドラゴンズ」の成功の方程式だと浜村氏は話す。現在,家庭用ゲーム機の「モンスターハンター4」や「THE IDOLM@STER ONE FOR ALL」「The Last of Us」「マリオカート8」などでも同様の手法で,「継続的に話題を提供して,ユーザーの心をつかむ」ことで結果を残していると語る。
もちろん,メーカーの施策だけでユーザーの興味を惹き続けるのは難しい。そこで注目したいのが「ゲーム動画および実況者」の存在だ。YouTube,ニコニコ動画,Twitchなど動画サイトはいくつかあるが,どこもゲーム動画は人気が高いという。YouTubeの大半は音楽やゲーム動画だったり,ニコニコ動画の52%がゲーム動画だったりと,ゲームの動画は大人気なのだ。
もちろん,メーカーが公式にアップしている動画もあるが,それよりも人気のあるゲーム実況者がアップする動画のほうが注目度が高いという。そういった人気ゲーム実況者を中心に大きなコミュニティが形成され,それがゲームへ「リテンション」に大きく寄与しているのだという。日本ではそれほどでもないが,海外では「eスポーツ」も同じような役割を果たしているとのことだ。
かつてスマホは家庭用ゲーム飲み込むと言われた時代もあったが,いまではスマホも家庭用ゲームも融合を果たしつつあり,それぞれの良いところを取り入れ,ボーダレス化していると浜村氏は話す。継続的に追加コンテンツを配信したり,各メディアやゲーム実況者と連携してしてユーザーを囲い込むことに成功したコンテンツだけが,現在の「ヒットコンテンツ」と言えるのではないかと話し,講演を締めくくった。
「公益財団法人 科学技術融合振興財団」公式サイト
- この記事のURL: