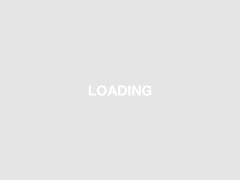イベント
[CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート
![画像集 No.006のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/006.jpg) |
セッションは「アニュビスの仮面」の紹介から始まった。
本作は前述したとおり,VR技術を利用したボードゲームだ。プレイヤーの1人はスマートフォンを利用するVRゴーグルを装着し,そこから見える風景(迷宮)をほかのプレイヤーに伝える。
それを聞いたプレイヤーは,(現実の)パネルを使って迷宮の地図を作る。最終的に作成した地図の上を,スマートフォン・アプリの指示に従って犬を移動させていき,犬が無事にゴールパネルまで到達できればプレイヤー全員が勝利するという,協力型のゲームである。
VRゴーグルはハコスコとの共同開発で,ダンボール製の組み立て式。このため,「アニュビスの仮面」はフルセットで3980円となっている。スマートフォンを別途用意する必要があるとはいえ,手軽に遊べる作品と言えるだろう。
![画像集 No.002のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/002.jpg) |
![画像集 No.003のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/003.jpg) |
![画像集 No.004のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/004.jpg) |
![画像集 No.005のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/005.jpg) |
今回のセッションでは,この「アニュビスの仮面」が制作事例とされたのだが,濱田氏はまず,「弱点というものは遊びになる」と語った。
典型的な例は「ジェンガ」だ。そもそも積み木で作った塔は「倒れやすい」という弱点を持つ。また,ジェンガの積み木は,サイズが微妙に異なっている。これらは「積み木で高い塔を作る」という観点に立てば,マイナスと言っていいだろう。
だが,こういった弱点なしには,ジェンガというゲームは面白くならない。これらの弱点は一種の「制限」であり,つまるところ「ルール」となるポテンシャルを持っているのだ。
![画像集 No.007のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/007.jpg) |
さて,この観点に立ってVRコンテンツを考えなおしてみよう。すると,VRコンテンツにはいくつか顕著な弱点があると分かる。
(1)VRゴーグルは1人しか装着できない
(2)VR酔いする
(3)VRゴーグルの中が蒸れる
これらの弱点に対して,濱田氏は「真正面から挑んで解決することも可能だが,非常に大変」と指摘する。氏はむしろこの弱点を制限とみなし,ルールへと落としこんでいくことで,これそのものをゲームにしてしまおうと考えたのである。
![画像集 No.008のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/008.jpg) |
このため,まず(1)の問題については,非対称型の協力型ゲームというデザインを利用することにした。VRゴーグルを覗き込んでいるプレイヤーと,それ以外のプレイヤーで,得られる情報や立場が違うということを前提にした(=非対称な)ルールにすれば,「VRゴーグルは1人しか見られない」という弱点は利点となる。
ちなみにこの「非対称型の協力型ゲーム」を考えるにあたっては,氏がWii U向けタイトルの企画を考えていたときのアイデアがそのまま使えたという。Wii Uのゲームは,Wii U GamePadという「(事実上)持っている人しか見られないディスプレイ」と,テレビ画面という「たくさんの人が見られるディスプレイ」の2画面で構成できるのが特徴で,VRゴーグルと同じ非対称性を有しているのだ。
![画像集 No.009のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/009.jpg) |
![画像集 No.010のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/010.jpg) |
(2)の問題については,VRゴーグルによる映像が「移動する」と酔いやすい,という点が課題だと氏は考えた。風景をその場で見渡すだけなら,装着者はなかなかVR酔いしないのである。
そこで濱田氏は,「だったら移動できないルールにすればよい」「その場で見渡せるだけにしよう」と考え,これによって逆に「観察し,共通点を見つけ,報告する」ことにプレイヤーを集中させた。そしてこの「観察と報告」は,「アニュビスの仮面」のコアとなるメカニズムでもある。
![画像集 No.011のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/011.jpg) |
(3)の蒸れる問題は,VRゴーグルを装着する時間を1分間に制限し,制限時間を過ぎたら次のプレイヤーに渡すというルールにすることで解決した。連続装用しなければ,蒸れることもないというわけだ。
もちろん,これによって参加者全員がVRゴーグルを体験できるというメリットもある。
![画像集 No.012のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/012.jpg) |
このように「アニュビスの仮面」は,弱点を利用することでより面白いゲームを作り上げていったのである。
さて,ここまでがセッションのいわば第1部である。氏はここから先を第2部として,ゲームデザインにおけるさまざまな手法を紹介していった。氏が紹介したデザイン手法には,独自の方法で名前がつけられているが,これは「名前をつけることで見解を共有でき,意見交換できるようになるため」であるという。このことはかつてCEDECにおけるナラティブの講演でも指摘された点だ。
最初に氏が提示したのは「両足モデル」と呼ばれるデザイン技法だ。これは「どれくらいゲームデザインや世界観を先鋭化すべきか」を測る技法と言える。
![画像集 No.013のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/013.jpg) |
濱田氏は,ゲームデザインと世界観をそれぞれ切り離してデザインするという。ゲームの構造が見えてきたら,さまざまな世界観を考案し,それにフィットする世界観を選ぶという手順である。そしてこの選択に,「両足モデル」が活用される。
例えば「アニュビスの仮面」の場合,ゲームデザインとしては「世界初のVRボードゲーム」という,文字通り「一歩先に進んだもの」だ。
そこに,先鋭的な世界観(「アニュビス」の場合,ハッカーが美術館に侵入し,監視カメラなどをハッキングしながら美術品を盗むという世界観も考えたという)を与えると,ゲームは「2歩先」に進んでしまって,プレイヤーがついてこれなくなる可能性が高まる。このため「アニュビス」では遺跡の探索という,多くのゲーマーに馴染みのある世界観を採用したというわけだ。
![画像集 No.014のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/014.jpg) |
![画像集 No.015のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/015.jpg) |
このように「あえて踏みとどまる勇気」(濱田氏)を得るにあたって,「両足モデル」はとても有効であるという。
これは逆も真で,濱田氏はいまVRボードゲームの2作めを作っているが,これはもう「世界初」ではないので,世界観には一歩先に進んだものを用意しているそうだ。
次は「タイムライン分析」。SNSとは関係なく,「ゲームを遊んでいる間にプレイヤーが何を感じ,どう盛り上がっているかを記録する」という手法だ。
ここで濱田氏は,「コンピューターゲーム畑の人からはよく,『アナログゲームはプロトタイプ制作が早い』とか『作るのが楽ですぐ実装できる』とかいった言葉が出るが……」と漏らした。実際にアナログゲームを作っている人なら分かると思うが,本当に面白いものを目指せば,そんなに簡単な話ではないのだ。
とくに問題となるのは,“なんだかどうも微妙な感じ”にゲームが仕上がっている場合だ。何がどう悪いのかが見えないのだが,なんだか駄目。こうういったことは珍しくない。
ここで登場するのがタイムライン分析である。
やり方は簡単で,ゲームをプレイしながら「面白い」「盛り上がっている」あるいは「なんかダルい」といった感情の上げ下げを,グラフで記入していくのだ(同時にそれぞれの段階で感じた感覚も記述しておくとよいようだ)。
この「盛り上がり・盛り下がり」は,あくまで主観的なものでよい,という。
![画像集 No.016のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/016.jpg) |
![画像集 No.017のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/017.jpg) |
「アニュビス」の場合,初期段階においては最初ぱっと盛り上がるものの,だんだん面白くなくなっていき,最終的には盛り下がってゲームが終了するというタイムラインを描いていたという。
そこでこの分析をもとに,冗長な部分をカットし,あるいは盛り上がりが欲しいタイミングに盛り上がるようなシステムを導入する。こういった改良点をピンポイントで見極め,作っていけるのが,「タイムライン分析」の魅力と言える。
最後に紹介されたのは「シャッターチャンス」で,これは技術というより心構えだという。
こちらも話は明快で,ゲームをデザインしていくにあたって「思わず写真を撮りたくなる瞬間」を意識して作っていくという手法だ。
「アニュビス」で言えば,プレイヤーがマスク(VRゴーグル)を被っている姿は写真に撮りたくなるし,完成した迷路も撮影したくなる。
![画像集 No.018のサムネイル画像 / [CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/018.jpg) |
ちなみに氏がこの「シャッターチャンス」を意識したのは,アナログゲーム「枯山水」の大ヒットを見てのことであるという。「枯山水」もまた,完成した庭を撮影したくなるゲームだろう。
これを踏まえて,VRボードゲーム第2弾は,プレイヤーが粘土を使って造形するというシステムになるという。「こんなものを作りました」というのは,確かに撮影意欲をそそりそうだ。
セッションの内容は以上となる。VRゴーグルによる非対称性を活用したヒット作としては「Keep Talking and Nobody Explodes」があるし,シャッターチャンスという概念は,スクリーンショットやプレイムービーのシェアが一般的となった現在,ほとんどのPC/コンシューマゲームタイトルで活用できそうだ。
CEDEC 2016では濱田氏以外にも多くのアナログゲーム開発者が登壇し,そのノウハウを語ったが,この動きが今度どのように発展していくのか,注目したい。
CEDEC 2016関連記事一覧
- この記事のURL:







![[CEDEC 2016]“弱点を利用するゲームデザイン”とは? VRボードゲーム「アニュビスの仮面」の制作者が語ったセッションをレポート](/games/999/G999905/20160831034/TN/019.jpg)